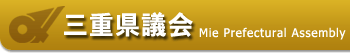三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成14年度 委員会会議録 > 平成14年12月17日 少子・高齢化・男女共同参画特別委員会 会議録
平成14年12月17日 少子・高齢化・男女共同参画特別委員会 会議録
少子・高齢化・男女共同参画特別委員会会議録
開催年月日 平成14年12月17日(火) 10:10 ~ 11:48
開催場所 第501委員会室
出席委員 7名
| 副委員長 | 田中 俊行 君 |
|---|---|
| 委員 | 清水 一昭 君 |
| 委員 | 山本 勝 君 |
| 委員 | 伊藤 夛喜夫 君 |
| 委員 | 島本 暢夫 君 |
| 委員 | 大平 誠 君 |
| 委員 | 西尾 文治 君 |
欠席委員 2名
| 委員長 | 野田 勇喜雄 君 |
|---|---|
| 委員 | 生川 利明 君 |
出席説明員
〔健康福祉部〕
健康福祉部長 青木 龍哉 君
経営企画分野
総括マネージャー 古庄 憲之 君
保健・子育て分野
総括マネージャー 村田 憲二 君
長寿・障害分野
総括マネージャー 大垣内 福己 君
〔生活部〕
人権・同和・
男女共同参画分野
総括マネージャー 上山 祐光 君
〔教育委員会〕
生涯学習分野
総括マネージャー 山川 晴一郎 君
その他関係職員
傍聴議員 1名
真弓 俊郎 君
県政記者クラブ加入記者 5 名
傍聴者 0 名
議題又は協議事項
少子化関係
・平成14年度少子化対策の実施経過及び成果を踏まえた平成15年度少子化関連予算要求状況
高齢化関係
・平成14年度高齢化対策の実施経過及び成果を踏まえた平成15年度高齢化関連予算要求状況
男女共同参画関係
・平成14年度男女共同参画対策の実施経過及び成果を踏まえた平成15年度男女共同参画関連予算要求状況
〔会議の経過と結果〕
〔開会の宣告〕
少子化関係
・平成14年度少子化対策の実施経過及び成果を踏まえた平成15年度少子化関連予算要求状況
高齢化関係
・平成14年度高齢化対策の実施経過及び成果を踏まえた平成15年度高齢化関連予算要求状況
男女共同参画関係
・平成14年度男女共同参画対策の実施経過及び成果を踏まえた平成15年度男女共同参画関連予算要求状況
(1)当局説明
〔青木健康福祉部長、村田保健・子育て分野総括マネージャー、大垣内長寿・障害分野総括マネージャー、上山人権・同和・男女共同参画分野総括マネージャー〕
(2)質疑・応答
○西尾委員 資料2ページにあります(3)の小児救急医療拠点病院運営の件ですけれども、医師不足のため未設置というところがありますね。今、それこそ少子化でお医者さんもちょっと経営面から見て、あるいは運営面から見て小児科を志望する先生が少ないということなんですか。それとも、どうしてこれ南の方にはないということなんでしょうかね。
そこら辺をちょっと伺いたいんですけれども。
○青木健康福祉部長 この(3)でございますけれども、これに関連して小児科医の不足については、これは全国的な傾向でございまして、これは特定地域のものではなくて、例えば大きな都市であってもやはり小児科が非常に不足をしていて、例えば夜間の当直体制が非常に組みにくくなっているという状況はございます。
特に、今回南志、東紀州の中で、一つこの拠点病院をつくりたいということで予算要求させていただきましたが、三重大学の小児科が中心になるわけですけれども、そこに入局をしていただく若いお医者さんが非常に少ない。それに引き続いて卒業、そこから研修が終わって地域に出向いていただく小児科の方が少ないというのも、これは県としてもやはり同じような状況でございまして、今回残念ながらこういう形になりましたけれども、これ何とか小児科、特に産婦人科も同じですけれども、こうしたことは地域の医療の基本でございますので、何とかこうしたお医者さんを確保して、この拠点病院につきましてもできるだけ、また早い段階で整備していきたいなというふうに思っております。
○西尾委員 今、全国的傾向とおっしゃられたけれども、国も少子化対策を重点の一つとして、政策の一つとしてやっておるんですが、やはり今幼児に対する医者の人数と言いますかね。どちらを、医者一人に幼児何人ということになるのか知りませんけれども、そこら辺で見て部長はお医者さんだからよくおわかりですけれども、そういうトータル的に見て日本全体的にどうなんですか。小児科の先生って少ないですか。多いんですか。
○青木健康福祉部長 子どもさんの数自体は減ってきているわけですから、子どもさん1人当たりのお医者の数はそんなに減ってるわけではないと思うんですけれども、やはり昔は例えば内科の先生が小児科もあわせて診ているというようなこともやっておったわけですけれども、最近は非常に各診療科の専門性が進んできたということと、やはりお母さん方を始めとして、受診に来る側もやはり子どもについては小児科医で何とか診てほしいということもありまして、昔はほかの科が診てた分、やはり小児科で今度はカバーしなきゃいけないということから、総体的にはやはり小児科医の不足というのが最近非常に言われ始めたということもあろうと思います。
○西尾委員 三重県も南だけじゃなくてということのようですけれども、やはりこの辺も少子化対策の重要な要素ですよね。
だから、いろいろ施策を並べられるけれども、一番基本的には健康というふうな管理をする医者というのが最も大事なことだろうと思うんですけれども、そこら辺もやはり今後とも少子化云々という以前の問題として、特に力点を置いてほしいとそんなふうに思います。これ要望しておきますけれどもね。
○大平委員 少子高齢化でちょっと聞きたいんだけれども、この少子化は私は歯どめはかからんのやないかなと、こう思うんですわな。いろいろ施策をやってもらったけれども。
三重県では1.3人ぐらいか。東京あたりでは今1.0人に、恐らく全国的にもどんどんこれ進んでいくと。介護保険できたんもそれだと思うんですわな。私は、ドイツへ行かせてもらったとき、ドイツが1.2人。これはもう家庭でどうにもならんから介護保険できたと。最近聞くと、ドイツやスウェーデンあたりは若干少子化対策、どういうふうにしてみえるのかわからんけれども増えてきた、こういうことを聞いておるんだけれども、基本的にはさっき虐待の話があった。もう子どもを育てる能力のない親が多いわけやな。こういう虐待。もうむしろ私はもう少なくなっていってもいいと思う。逆にそういう意味からいくと。
そういうことで、将来的には私は移民というか、外国からもう人を連れてこなしようがないというように日本もなるんじゃないかな。現実に、三重のくにづくり宣言見たって、今186万県民あるのが50年には150万になる。計算上、このまま行ったら1,000年先の日本の人口ゼロやと、こういうような結果が出るわけやな。
そこで、問題なのは私は基本的にはやはりその子どもを育てる環境の整備ですね。いろいろこうやって施策を並べているけど、例えば県庁一つを例にとっても、その男子職員でも育児休暇ですね、恐らくこれとっておる人はごくわずかやないですか。この間聞いたら1人か2人やと。来年とるのも、僕ちょっと知っとるのは2、3人おるけれども。だから、やはりそういう休暇がとれない環境があるわけやな。これは何も県庁だけやない。県庁がそれやったら、民間企業でも推して知るべしやな。
やはり、子どもが女性にしても男性にしても、そういう環境づくりの方が僕は大事だと思うんやけどね。そこら辺、どういうふうに感じる。どんな施策をするよりも、一番僕はそれが大事やと思うんやな。
県一つとってもやよ。また、休める条件なり、今日は女性の職員少ないけどな、女性の職員でこれから管理職になってとにかく休めん状況出てくるでしょう。そういうところに、いろいろ公共でも民間でもそういう問題が横たわっておると思うけれども、まずそこら辺一遍どう考えてるのかな。 まず最初にちょっと聞きたいな。
○青木健康福祉部長 行政が行う少子化対策の目的なんですけれども、やはり子どもをつくるとかつくらないとか、産む産まないというのは基本的にやはり個人とか家族の選択によるところが多いと思うんです。
ただ、これは国の調査ではあるんですが、今、結婚している家族に聞いたアンケートの中で、実際に持っている子どもと本当は何人産みたいのかという2つの数字を聞いたデータがありまして、実際に産んでいる子どもの数、これは結婚している家族だけですから2.1とか2という数字で、ただその人たちが本当に持ちたい子どもというのは2.5とか6という数字で、そこに0.3とか4という数字の差がございます。
結婚したけれども、本当に今持ちたくない。実際にも持ってないという人の選択をどうこうするというのはなかなか難しいとは思いますが、本当に持ちたい子どもの数と実際に持っている子どものすき間を埋めるというのは、やはりこれは行政としてある程度やっていかなきゃいけないことかなと思ってます。
じゃあ、そのすき間がある理由を聞きましたところ、やはり仕事と家庭が両立しにくいでありますとか、教育の非常に負担が重いでありますとか、子育てに対しての不安が大きいとかそうした原因が出てまいります。
今、いろいろ施策を説明してまいりましたが、主な理由としてはそうしたアンケートに基づいて実際に子どもを産みたい人にとってバリアになっているものをできるだけ支援していく。具体的には仕事と家庭が両立できるように放課後児童クラブというようなものをつくっていって、5時とか6時ぐらいまで子どもをちゃんと見てくれるような場所をつくりましょうでありますとか、地域の中で子育てを支援してくれるような地域子育て支援センターといったものをつくっていきましょうといったことを今行政としてはやっていくというのが基本的な考え方でございます。
○大平委員 本当にこれは難しい問題やと思うんですわな。 今おっしゃるように、個人の選択、これはもうそのとおりだと思うんですわな。それともう一つは、最近は男女とも結婚しないわけやな。これは子どもできんわけやわな。本当に私らの周囲の女性見たって、ちょっと結婚どうやって、私の事務所におる女の人も鼻で吹いとるわ。もう42にもなってな。全然話にならん。
それは、やはり収入があって男以上の収入があったら、そらそういうのは多いわ。男でも結婚しない人ようけおりまっせ。今ね。だから、結婚して子どもの問題あるし、結婚しないのが増えておる。
だから、もう今の話を大きな選択に任せなしようがないわけやな。だから施策、じゃあ結婚しなさいというような、県が指導もできんしな。結婚のあっせん所もできんやろうけどさ。いずれにしても、これ難しい問題で、ただ行政としてできることは、やはり子ども産める環境づくりを私はひとつお願いしておきたいなと。
それからもう一つ。最近年とってきたんで老人問題で一番、私特養の問題かな。さっき説明受けたけれども。それで、在宅介護は私はだんだん今の話、高齢化してくるともう限界に来て、どうしても特養のお世話にならなあかん。私どもの周囲でもよく頼まれるんだけれども、特養に早く入れてほしいんだけれども、なかなか順番回ってこない。待機者が、恐らくこの県の数字と僕らが知ってる、また肌身で感じておる数字と違うと思うんやな。だから、やはり今どうしても松阪あたりでは半年ぐらい待たなあかんというのが実態ですわ。だから、何とか早く入れたってくれって言ったら、お医者さん、死ぬの待ってもらわなあかんなって、こんなんあんた悲劇やわな、こら。そういう状態ですよ。
そこで、この15ページにもさっき説明受けたけれども、こんな数字でええのかな。平成19年度に1,069人か。平成14年に比べてね。こんなもんとても私は追いつかんと思うんやわ。
それで、一つお伺いしたいのは、実際のこういう数字が予測できる数字はもっともっと多いんではないかな。僕らが今待機している実態から見てね。
それから、もう一つここに書いてある入所の必要の高い方が優先的に入所できるための指針をつくるなんて書いてもうてあるけれども、現在申し込んでいる人はようけあるんですわな。ずらっと並ぶのと、今度は飛び越えていく人はできてくるな、これやと。申し込んでおっても。
だから、入所の必要なというのはどういう基準になるのかな。とにかく申し込んで、とにかく一日でも早く入れたいという人があるのに、それ飛び越えられるとこれまたね、死ぬのを待てと言われておって、本当に入るまでにみんな死んでしまうわな。
そこら辺の見解はどうなんかな。ちょっと聞かせてほしいんやわ。
○青木健康福祉部長 まずこの15ページの1の1,069の数字でございますけれども、介護保険計画、介護保険につきましては、各市町村が実施主体となっておりまして、各市町村が自分の町でどの程度の入所サービスの利用者があるのかというのを、在宅も含めてサービスがどのぐらいあるのかというのをまず計画をして、その計画に基づいて例えば保険料を算定するといったようなことをするわけでございます。
県がやりますのは、その計画を支援するというのが県の業務でございまして、ここに出ておる数字は各市町村が自分の町の計画をずっとつくってきたものをこちらに出していただいて、それを単純というか、ある意味足しあげたものがこの数字になっておりますので、一番この現場に近いところにあります市町村が把握をしているものを足しあげたものというものでございます。
この数字と実感とがちょっと違うんじゃないかというお話が次でございますけれども、例えば特養も実際に一つが空きましたということで、その施設が待機の申し込みをされている方に連絡をするといった場合でも、例えば一番目に挙がっている人たちがすっと入ってくるケースもございましょうけれども、実はちょっとまだもう少し在宅でできるからでありますとか、そういう状況で順番がずっと下がっていって、とにかく申し込みはするけれども、それはちょっと予防的に悪くなったときに入りたいからやってるだけだというような人も随分おられるのが実態のようでございます。
ですから、今回考えております申し込みとか入っていただくための基準づくりともうしますのは、そうしたいろいろなケースの方がおられますので、そうした中でより緊急度の高い人たちをどう選定して、その人たちに入っていただくという基準づくりをするということで、本当に必要な人がやはり入っていくというのが一番ふさわしいと思いますので、そうした基準をつくっていくということでございます。
○大平委員 基準は、まだこれからつくられるわけやな。入所の必要度が高い方が優先入所できるための県としての指針の策定、公表を行うという。だから、これはこれからつくられるということやな。
○青木健康福祉部長 今、まさにこれをつくっているところでございまして、これも県から強制的にするということではなくて、各施設の代表の方などに集まっていただいて、実際の現場で使えるようなものをつくらなければ意味がありませんから、12月の今終わりぐらいにもう1回検討会、16日だったですかね。開きまして、そこで試案をつくりまして、来年になりましてそれを実際に幾つかの特養等で運用してもらいまして、それが実際に現場で妥当なものかということの検証をしていっていただく。
最終的には、年度末ぐらいまでに県の指針の目安ですけれどもつくりまして、それに基づいて各施設が自分のところの基準をちゃんとつくっていただくというような手順になってます。
○大平委員 結局、介護保険ができたのは、在宅介護が基本でやはり家庭で介護というのは、やはり老人も希望しているわけですわな。しかし、家庭でとにかくもう面倒は見きれないというのは随分今増えてますわ。そうなると、やはりこの特養へ一日も早く入れてくれというのは、本当に現実的に松阪を例にとると半年ぐらい待たんならんですな。私が見とってね。
だから、需要が満たされないという状況にある。だから、この数字以上に私は多いと思うんですわ。
その点十分ひとつ認識していただいて、やはり特養は、究極は僕は特養にあるように思うんや、今ね、この老人問題は。これだけひとつお願いしておきます。 以上。
○清水委員 大平委員の質問に関連して。特養の件なんですが、例えば私も相談を受けた件なんですけれども、脳梗塞なんかで入院されてて医療処置が終了した。そして、その方はもう配偶者もいなければ子どももいないし、親戚の方々もいなくて、もうどなたも面倒を見る方がいないわけですよね。
しかし、もう処置が終われば病院から出ていかなきゃいかん。それで、特養なんかを申し込んだら、鈴鹿なんですが、もう200人ぐらい順番待ちで待ってるような状況で、なかなかそれでも入れないという、こういうこの方たちのセーフティーネットというか救済する措置というのは、これどう考えてますか。
○青木健康福祉部長 まさに、御指摘のような非常に緊急度の高い人がおられるんですけれども、そういう方が今はある程度申し込み順になっておりますので、なかなかその上に行くことがないということで、例えば申込者が今6,800人ぐらいおるという集計表があるんですけれども、例えばその中で本当に在宅にいる方は半分ぐらい。ほかの方は、もう既にどこかの施設に入っている。中には、もう別の特養におられる方もおられるんですね。そうした人が半分ぐらいおられて、その中で例えば介護度の4とか5といったような非常に重症の方もこれも3分の1ぐらいで、あとは軽症の方がおられるとか。
あと、本当に身よりのない一人の方、またはお年寄りだけの家庭の方、これもまた3分の1ぐらいでございまして、実際には4、5百人が非常に緊急度の高いというような内容にもなっておりまして、そうした方がちゃんと順番はある程度考えなきゃいけませんが、本当に必要度の高い人が入れるというルートもあわせてやはりつくっていくというのが今回の基準づくりの目的でございますので、まさにそういう本当に急いでおられる方も、今回からはできるだけ何とか対応できるようにしたいなと思っております。
○清水委員 現実に、今現在もうそういう方がみえるんですよ。先ほど、部長の説明によると15年度末に指針を公表して、それから各施設で運用するということですよね。そうすると、やはり1年以上も開きがあるということで……。
○青木健康福祉部長 今つくっておりますので、14年度末で。今12月ぐらいまでに大体目安ができて、来年の1月ぐらいにちょっと試行してみて、最終的には3月ぐらいから決めて、14年度の末でございます。 ですから、もう数カ月ということで考えております。
○清水委員 それは、もう各施設によってその指針というのは決められて、統一されたわけではないですよね。県全体のあれでは。
○青木健康福祉部長 基本的なルールは、今、各施設の代表の方に集まっていただいてつくっております。
やはり、各施設で例えば地域事情だとか若干ございますから、そこは共通の案をベースにして各施設で独自のものをつくっていただくというのがこれからの作業になります。
○荻田長寿社会チームマネージャー ちょっと今の入所基準の策定状況を補足させていただきますと、今部長が申しましたように、12月中に大体試行案というのをつくります。それによりまして、1月ぐらいに説明会を開催させていただいて、それで施設の方、それから市町村の方に説明させていただいて、1月、2月ぐらいで試行していただく。それで、3月に県の指針を確定するということでございますので、試行も大体そういうような優先的な入所をやっていただくというような形になろうかと思います。
それで、今その基準が大体どんな形になっておるかと言いますと、大体今の案では申込者を3段階に分けまして、一番緊急に入所が必要な方というのと、その次に優先的にされるような方と、それからあとは順番で申し込み順でいく。大体3段階に申込者を分けるような案になっておりまして、一番目の緊急はどんな人か、ちょっと虐待が見られるとか介護放棄が見られるとか、本当に緊急に入所してもらわないといけない場合を想定して、それはもう措置というような形も考えられるんですけれども、そういうような場合は一つ、特急、そういう鉄道で言うと特急と言うんですかね。特急のような感じの一つをつくって、あと申込者を介護度とかそれから家族の状況とか、それから介護サービスの利用の状況とか、あと待機してみえる期間ですね。こういうのも勘案しながら点数づけをしまして、それでその点数のある一定のレベル、例えば100点満点なら80点以上の人については、それはそういう方は優先的にさせていただくというようなこと。それ以下の方については、そういう緊急性も認められないというような方ですので、空きができた段階で申し込み順で入っていただくというふうなことを考えております。
それで、これは先ほども部長が言いました県としての指針でございまして、この指針をもとに各施設の方で、各施設の指針をつくっていただく、入所基準をつくっていただく。それで、施設はその基準に基づいて実際のその申込者に対してどの方を入所いただくかというのを決定していただくというふうに考えております。
○清水委員 そうすると、施設によってきついところと緩いところが発生すると、ある程度また申し込みの希望者の方がある施設に集中したりとか、そういうふうなことが考えられませんか。
○荻田長寿社会チームマネージャー 施設に一応それで私どもこの県の基準が、県としての指針が出るということでありますと、それも一応公表させていただきます。それと、その施設は施設で自分のところでつくったら自分ところのその基準というものを公表していただく。それは、ちゃんと説明責任を持ってしてくださいよと。
だから、一応県は県の基準というものがございますので、それが違っておったらお宅はどういう理由でそこら辺は違うようにしたんでしょうかとか、それを利用者の方にちゃんと説明していただくようにお願いしますので、そんなようにそういう説明ができるような内容の基準をお願いしとるということで、そんなにこう何て言いますか、よほど県の指針と違うというようなことはないと思いまして。
あとは、サービスの入所申込者が行きたいとか行きたくないという選択の中身については、やはりそういう施設のサービスの内容がいいところへ、やはり将来的にはそういう高齢者の方も行きたいと思うようになると思いますので、その入所基準によるというよりも、その施設自身の介護のサービスのレベルを上げていくというような方が、より重要ではないかなとは考えておりますけれども。
○山本委員 それにちょっと関連して、北勢地域の件ですがね。桑名、四日市の方でも、特養に入りたいという人、大体100人ぐらいおると言って、なかなか順番が入れてもらえやんということで、確かにようけ見えるんやなと、こうやってこう思うんですけれども、今いろいろ県としての指針を出すということであれなんですけれども、そういうところでグループホームというのを最近いろいろどんどん出てきましたわね。その辺の絡みのところ、例えば僕はすみ分けをある程度やっていかんと、今の特養なんかというのをどんどん入れていっても、ベッドの病床数なりそれは決まっておるんやから、今大平委員からあったように、中に入ってみえる方が例えばお亡くなりになるとかそういうことがなきゃなかなかかわって入ることはできませんから。そういう意味で何と言うかね、重度と軽度から含めて、グループホームとの絡みというのをもうちょっと整理された方がええんやないかと思うんやけど、そんな考えはどうですか。
○荻田長寿社会チームマネージャー グループホームにつきましては、今、グループホームで介護保険が適用できるというのは、痴呆対応型のグループホームということで、痴呆があると言われる方が入るグループホームが認められている。そして、これちょっと専門的な話なんですけれども、介護保険上はいわゆる施設というのは特養と老健とそれから介護療養型病床、この3施設でございまして、いわゆるグループホームというのは、今、介護保険上は在宅のサービスの扱いになっております。これちょっとあれなんですけれども。
在宅につきましては、ちょっと参入の規制緩和が行われておりまして、これまで施設については社会福祉法人とか医療法人というそういう法人でないといけないんですけれども、在宅系はそれ以外の営利法人、企業とかそれからNPOというような方も参入できるというような形になっておりまして、そういうことですので、今グループホームというのはかなり増えておるというのが現状でございます。
ただ、ですけれどもやはり施設としてはすみ分けがあろうかと思います。やはり特養なら特養の、昔はそういう寝たきり、それに近い方が入所されるというのが特養でございまして、グループホームというのはその寝たきりというよりも、そういう自分でいろいろなことはできるけれども、そういう痴呆とかやはり問題があるということで、そういう家庭で介護できないというようなことでグループホームというような、そういう使い分けをしながらこう今増えておるグループホームを活用していくというようなことで、一つはそういう待機者の解消にもなるんではないかなというようなことは考えておりますけれども。
○山本委員 確かにそれはようわかるんですけれども、特養あたりに、もうとにかく体はそんなに悪くないんやけれども、痴呆症が進んで4、5ぐらいんところで何ともならんということで、とにかく施設に入れて家族では持ちこたえられないので入れてくれというのは、よく現状としてあるわけですね。
そんなときに、例えば特養なんていうのはベッド数が決まっておってなかなか入れんわけですよね。
現実に、そうやって構えてせっぱ詰まっておるんやから、そういう意味ではもうちょっと僕は、例えば特養やったら寝たきりの重度の者しかそういう対応しかできやんという中で、例えば現実的には健常やけれども痴呆症がひどいものやから入ってみえる人もいるわけです。特養の中にも。
今言われたのでいくと、ちょっと話が違うなという感じがするもんで、やはりもうちょっとそういう今規制緩和がどんどん進んでいくような状況の中から、そのグループホームというのをいろいろ活用していくような時代になって先取りをしていくような時代になってきてるのと違うかなと思うのやけれども、今現実的にその需要に対応していくためにはやらざるを得んのと違いますか。
○荻田長寿社会チームマネージャー これ先ほどの入所基準というのを説明させていただいたんですけれども、その入所基準で新しくそういう入ってみえる方を優先的に入所するという基準は、当然その介護度が高くて、それでそういう介護が必要な方が特養に優先的に入所するという形になりますので、この優先的な入所基準を運用することによって、特養自身は介護の重い方がやはり増えていくという傾向にはなろうかと思います。
そういうことで、将来的にはグループホームなんかにも移っていく方も増えるんではないかなというふうには考えておりますけれども。
○山本委員 ありがとうございました。それと、児童虐待の方をちょっとお聞きしたいなと思ったんですけれども。
これ難しい状況で、この対応も24時間対応していかなあかんということで、大変僕は難しいなと思うし、努力もある程度されておるなというこんな気がするわけですけれども、やはり事象が起きてきたときには、その対応については決して100%満足にはなかなかいかんというのは、これ四日市の例でも見てるように出てきてるわけですけれども、出てきたことの事象に対して対応するというのは、これはまあ本当に大事なことなんやけれども、そのもとの原因はやはりどんどん排除、つぶしていかなあかんということなんやけれども、これは今の社会、教育の問題なり社会のこの仕組みの問題等でもあるかわからんのやけれども。
7ページにずっとこれ虐待の種別と書いてあって、相談の件数とかそれから虐待者の別ということで書いてあんのやけれども、虐待をする人がどんな心理でどんな原因でなぜこう虐待をするかというのは、以前も僕お聞きしたかもわからんのですけれども、出てきとらんわけですね。
例えば、虐待の種別でも身体的虐待やったら体を何かいじめての虐待かわからんし、いろいろこうあれですけれども、虐待者の中には実の母というのは213、それから実の父というのは81人おるのやけれども、この辺の人が虐待をする心理と言うんですかね。原因と言うんですかね。例えばもう育児にせっぱ詰まったということとか、それからいつも自分はかっとして切れるんやというようなあれとか、いろいろ僕は原因、その虐待をするときのやはり虐待者の原因があると思うんやけれども、この辺のところはちょっと一回わかる範囲で、もしあればちょっと教えてほしいなと思ってる。
○村田保健・子育て分野総括マネージャー 虐待が起こるケースといたしまして、やはり今度新しく新価値でも考えておるんですけれども、創造予算で考えておるんですけれども、マニュアルをつくろうとする中で、やはり10代の若い母親とかそして自分が子どものときに虐待を受けた方が多いとかというようなことが、それぞれ専門家の話では言われております。
そして、今回の四日市のこの件でも、実は児童相談所へ相談があったときは、子どもを育てたくないということで、いわゆる自分が母親としての自覚がないというんでしょうかね。そういうところがございまして、それでやはりその辺をもう少し母親としての自覚を持たすか、子どもをどうやって育てたらいいのかというのがなかなかわからない面もあるというようなこともございます。そういう昔はいろいろ親がいて、いろいろ相談とかそんなこともあったんですけれども、最近は地域のいわゆる支援をしてくれる人もなかなかなくなっている。昔はあったんですけれども、なくなってきたというようなことで、なかなか親としてやれるところが少ないというようなこともございます。
それで、今回これからの新価値創造予算でどうなっていくかわかりませんけれども、県としましては今回のケースをもとにして、いわゆる母親が実際にこのように子どもを育てたくないと言ったときに、そのときに実際そういう子育てについて体験というか経験できる場をつくってみてはどうかということで、結局今乳児院というのが県内にございまして、小さなお子さんを預かっておるところが津と四日市にございますが、そこにそういうような場合の話があった場合に、現実にお子さんは乳児院の方が預かってくれるんですが、母親はそういうことでは全然乳児院ではだめですので、できましたら母親のちょっと部屋をつくって、そこでちょっとしばらくショートステイみたいな格好で滞在しまして、実際に子どもを育てるというんですか、そういう体験というんですか、そういうことができたらどうかなというふうなことで、今実は今度の新価値創造予算で要求していこうかなということで、今考えておるようなことでございます。 ですから、いわゆる母親というんですか。親育てというんですかね。そういうものが非常に重要になってきておるなということでございます。
○山本委員 確かに、今言われるようなそんな世の中になってきたかもわかりませんのやね。 そやで、そう言いながらもやはりそれの事象がまた起きてくることはどんどん起きてくるんやで、こういう子どもを育てるという研修を親がするということもそれは必要なんかもわからんもんで、やはりその原因というのをもうちょっと何か対応できるような、そんなような施策というのもやはりどんどん出してもらうべきかもしれんね。 ここの中では、ちょっと余り具体的に見えてこんもんやしあれですから、ひとつまた頑張ってください。
○西尾委員 今の山本委員の関連ですけれども、虐待の問題ですけれども、自然界の鳥類の親が子を産んで育てる。非常にこう自然環境の厳しいところで、岩場であろうとあるいはまた雪の下であろうと、ああいうのをやはり今まで人間が万物の霊長って威張っておったけれども、今僕は一番そういう意味では最低になっておると思うんですよね。
だから、もっともっと本当の親子のあの愛情とかきずなとか、そういった人間の心というのをやはりもっと教育せないかんのと違うかと。僕は一番そこら辺に原因があると思う。やはり、産んだ子ども、ちょっとよく泣くからとかせっかんして、ちょっと経済がえらいからと言って食事を与えないとか、いろいろやってる、最近はそういうことが多いんですよ。だから、僕は本当に自然界の中で、人間が僕は一番恥ずかしいなと、こういうふうな思いをするんですね。
だから、そういう意味で、これからもっともっと人間の心、愛情という観点をこれは教育の場が中心にならないかんのかもしれないけれども、いろいろな場で家庭教育の中でも含めて、やはり精神的につくり上げていかねばならないのではないか。そうしなきゃ、解決しない。
いろいろと今総括マネージャーが今後の取組とか対応も、それから説明を受けたけれども、やはりそれは一つの事象に対してこうしますであって、この虐待問題も本当は県の職員が、あるいはその関係担当者云々という以前に、これは昔は本当にこういうことがあったら大ごとで大変で、皆さんが献身的にお世話をしよったわけですね。それが今なされてない。本当に一つのレベル以下になってしまったと、そこら辺に原因があると、このように思うんですよね。
だから、これから行政においてもただ事務的に次から次に手を打つんではなくて、もっと精神的な面に入る必要があると、このように思うんですけれどもどうでしょうか。
○村田保健・子育て分野総括マネージャー 西尾委員の言われるように、私も最近特にその辺のことを考えておりまして、本当に人間というものにつきまして、どんな動物の世界、何にしろ、親が子どもを育てるのは当然であって、虐待ということは本当にもう考えられないというのが通常の世界でございます。
私も、そういう意味でやはりこれからは教育と言うんですかね。そういう母親に対する教育というんですか、そういうのを本当に小さいときから育てていかなだめだと思っておりますので、今後もまたその辺につきましてはいろいろな事象で話をして行きたいと思いますし、教育とも連携を深めていきたいというふうに考えておりますので、と思っております。
○西尾委員 だから、健康福祉部の方でも講演なら講演を持たれて、あるいはシンポならシンポでもよろしいけれども、常に本当の人間の心、愛情というものをテーマにしたそういう講演とか研修とか、ほかのことはまず横に置いておいて、そういうことばかりで人間の心とか精神とか、そこら辺からもっと広めるようにしてもらいたいなと、このように思いますけれども。 何かあったら。なければよろしいです。
○村田保健・子育て分野総括マネージャー そういう愛情とそういう意味での今後努力をさせていただきます。
○伊藤委員 簡潔に言います。
児童虐待に絞るんですが、基本的には少子化や児童虐待や少年の問題や老人の問題は、これは国家的な大きな課題なんですね。そういう中から考えますと、今の地方分権も含めて今のこれからの時代は、この大きな国家的な課題というのは、例えば端的に言うと国が財政的な支援をする。そして、都道府県、市町村は政策的なものをきちっと構築していくということですね。
その順序からしますと、国は財政的な支援をして、一番の根っこはこういう問題の解決の根っこは、まさに市町村なんですね。だから、私は国のこの問題に対する施策について、都道府県、市町村は国から劣っておったらだめだと思うんです。最初ね。施策としてね。それが一番大事だと思うんですね。
そういう中で考えてきますと、例えば児童虐待の問題、今ちょっと出ましたけれども、顕在化された対策と潜在的な対策とあるんですね。ちょっと出ましたけれどもね。
むしろ、顕在化された対策は割と不足ながら対応しやすいんですね。潜在化された対応をどうやって構築していくかということをしっかりと議論しないと、私はこれはもう解決にならんと思うんだね。それほど大きな問題だと思うんですね。その潜在化された対応はどうやってやるかと言うと、やはり僕が言うたように、市町村なり民間におりていかないかんと。県のやられることも限界がある。国がまして限界があるということからすれば、この中にありますように四日市の悲しい事例が出たんですけれども、例えば市町村とかNPOとか民生委員とかありますね。市町村は行政ですから、それは県の並びへ来るとしたら、例えばNPOとか民生は民間ですね。これを考えた場合、こういう問題に対する職業観があるかどうか、一つはね。
役目としてマニュアルを持って頭にわかってやらないかんなというのは、民生委員の人とかNPOの人はそれを専門的に本当に自分の性格がそうで、そこへ突っ込んでいくというそこまで職業観はないわけですね。求めるのも無理だ。しかし、可能ならばそこへ行ってほしいわけですよね。
だから、NPOとか民生委員の場合は、私は職業観がそこまで行かないと思う。民生委員の人には気の毒だけれども、一生懸命まじめにやってます。僕らも知ってます。しかし、職業観から見たらそこまで必死の気持ちはないですね。そら当然必要ない。
だから、私はNPO、民生委員の末端でのこういう活動は非常に大事ですけれども、一遍議論をして、部長ね。もう一つ第三者的な機関を一遍新しく発想をかえて、従来型の地域でやれるという固定観念はちょっと横へ置いておいて、この大きな問題について単純なNPO、民生委員じゃなくて、もう少し一遍これは答え出てこないと思うけれども、この潜在的な要因ですね。潜在的な要因に対する第三者機関をつくって、それがNPOや民生委員の活動にさらに効果ができて上回るという、そういう活動体ができんかなとよく思うんですよね。
だから、顕在化された問題はマニュアルでいきますけれども、潜在化された問題というのはマニュアルではいきませんから、その辺が部長のものすごい大きな課題で長期的な課題だとは思うんだけれども、そういうことを一遍発想をころっと変えて、一遍議論されたらどうかなと思うんだけれどもな。 どうでしょうかね。
○青木健康福祉部長 今、委員御指摘ありましたように、県の対応というのは基本的には児童相談所の対応で、児童相談所というのは何かがあって、もう顕在化したものについての事後的な処理というのがこれまでの対応の中心でございまして、潜在的にまだ起きていないものを未然に防止する、早期に把握するというのが次の段階で、本当はそこがすごく大事なわけでございますが、ただ、この段階をやはり県だけで対応するのは、これはとても対応が難しいわけで、やはり市町村とかあとNPOとかそれ以外の一人一人の県民のレベルまである程度協力をお願いしないと、なかなかそこまではいかないんじゃないかなという気はしております。
それで、ただ実際どういうふうにしてそういうシステムをつくっていくのかというのはなかなか難しいわけでございますが、一つ今年からやっておりますので、例えば北勢地区、四日市の方で子育てキーパーソンのモデル事業というのをやっておりまして、これは虐待だけでもないんですけれども、地域の中でそういう自分の子育てがある程度終わったような人、また子育て中の人も含めますが、そういう人たちに子育てのNPOの人たちに研修をしてもらって、そこで虐待でありますとかそういう子育てのアドバイスをするときの技術的なノウハウなんかも学んでいただいて、そういう人たちが地域の住民の中にまざっていって、そこでこうある程度早期にそうした情報を集めていただくとか、アドバイスをしてもらうといったようなことも少し試み的にやり始めておりまして、そうしたものをちょっと今年始めたものですからまだまだ結果は出ておりませんけれども、有効性がどうかというのも検証しながら、ちょっと全県的にどうしていくかというのも考えていきたいなと思っております。
○島本委員 私だけ何にも言わんというのも……。
地域のことを言って申しわけありませんけれども、東紀州地域というのはこの本を見ると高齢化率、やはりいつも一番ですね。人間は少ないけれども、やはり高齢化率はひどい。子どもは一人前に産むんですけれども、やはり少ない所得の中で一人前にしたら学校へ行くのに送金したりしてるんです。そして一人前になったら働くところがないから、津や四日市や鈴鹿やそこらで働かせてもらって、名古屋、東京、みんな都会へ出ていくんです。だから、高齢化率が高いんです。
その地域で働かせてもらってるから、当然税金もその地域へ払う。親が一番えらいんですね、子どもを大きくするのに。大きくしたらもう出ていくんです。
国の財政支援等も勘案すると、思うんですけれども、今大平委員が言ったように、順番待ちの人が多いんですね。率からいくとね。人間の数は少ないですが。
その施設をつくるのに、許可というのは国の財政支援とかまた県の財政状況とかいろいろ勘案して許可を与えると思うんですけれどもね。その高齢化の介護する施設とかね。これは平等に県は考えてやっておると思うんですけれども、率がやはり少ないというか、人間は少ないからしようがないんですけれども、もっと高齢化率が高いから、率も勘案して待っている人を入れたってほしいということで。若い人が出ていっていないんですから、やはり施設等の許可、いろいろな施設あると思うんです。高齢化に対する施設、そのことを要望だけしておきます、東紀州に対して。地域のことを言って申しわけないですけれども、平等にこっちもやってほしい。国から、国の財政的な支援というのはみんな要望してようけとってきてほしいということなんです、第一義的に。それから、それを配分するときにやはりこっちの東紀州地域は施設がやはり少ないということで、また地域のことを言って申しわけないですけれども、こっちもちゃんとして、地域のことも考えてやってほしい。特に要望しておきます。終わり。
○田中副委員長 要望でよろしいですか。
○島本委員 はい。
○田中副委員長 ほかにございませんか。ほかになければ、これで調査を終了いたします。
当局には御苦労さまでございました。
委員以外の方は、退出願います。
委員の方は、御協議願うことがありますので、そのままお待ち願います。
〔委員協議〕
その他
(1)今後の委員会の開催について特別な調査事項が生じない限り今回をもって終了
(2)中間報告について正副委員長に一任
〔閉会の宣告〕
以上、会議の要綱を記し、ここに押印する。
平成14年12月17日
少子・高齢化・男女共同参画特別委員会副委員長
田 中 俊 行