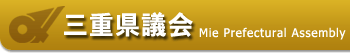三重県議会 > 県議会の活動 > 全員協議会 > 全員協議会議事概要 > 令和6年度 全員協議会議事概要 > 令和6年12月5日 全員協議会概要
令和6年12月5日 全員協議会概要
■ 開催日時 令和6年12月5日(木) 14時57分~15時52分
■ 会議室 全員協議会室
■ 出席議員 46名
議 長 稲垣 昭義
副議長 小林 正人
議 員 龍神 啓介 辻󠄀内 裕也
松浦 慶子 荊原 広樹
伊藤 雅慶 世古 明
吉田 紋華 石垣 智矢
山崎 博 野村 保夫
田中 祐治 芳野 正英
川口 円 喜田 健児
中瀬 信之 平畑 武
中瀬古初美 廣 耕太郎
倉本 崇弘 山内 道明
野口 正 谷川 孝栄
石田 成生 村林 聡
田中 智也 藤根 正典
小島 智子 森野 真治
杉本 熊野 藤田 宜三
東 豊 長田 隆尚
今井 智広 服部 富男
津田 健児 中嶋 年規
青木 謙順 中森 博文
山本 教和 西場 信行
中川 正美 日沖 正信
舟橋 裕幸 三谷 哲央
■ 欠席議員 なし
■ 県政記者 1名
■ 傍聴者 2名
■ 協議事項
1 「三重県人材確保対策推進方針(仮称)(中間案)」について
(1)時間 14時57分~15時52分
(2)説明者
知事 一見 勝之
[総務部]
部長 後田 和也 その他関係職員
[政策企画部]
部長 小見山 幸弘
次長兼ひとづくり政策総括監
兼ゼロエミッションプロジェクト総括監
兼プロモーション総括監 世古 勝
その他関係職員
[地域連携・交通部]
副部長兼交通政策総括監 中村 元保
次長 西田 正明
次長兼南部地域振興企画課長 山本 佳子
[医療保健部]
副部長 西口 輝
その他関係職員
[子ども・福祉部]
次長兼子ども政策総括監 髙山 功太
その他関係職員
[環境生活部]
部長 竹内 康雄
その他関係職員
[農林水産部]
副部長 山添 達也
[雇用経済部]
部長 松下 功一
その他関係職員
[観光部]
副部長 福島 賴子
[県土整備部]
副部長 上村 告
[教育委員会]
副教育長 大屋 慎一
(3)説明内容
別添資料のとおり
(4)質疑の概要
○杉本議員 取り組むべき方向性の1つ目に、ジェンダーギャップの解消と働きやすい職場環境づくりを位置付けたことを高く評価する。女性の正規就業率がL字カーブになっていることは課題であり、労働力不足の状況なのに女性の労働力が潜在化して活用されていない状況を解消する必要がある。進路の選択時等の女子生徒への学校教育、家庭教育がL字カーブの要因になっている可能性がある。女性は子育てしながら働く等のアンコンシャス・バイアスのもとで女性が育っており、働き方の選択として非正規が主になっている可能性がある。女性が正規で働ける社会になっていないとも言える。職種も男性向け、女性向けに分かれてしまっている。ものづくり現場、工場の中に女性の姿が少ないのは変えていく必要がある。この方針の中に、このような教育の観点も加えてほしいと思う。
○世古次長 進学時や職業選択時におけるバイアスの解消は重要である。方針への盛り込み方は産学官連携懇話会の中で議論する。
○石田議員 人材の確保において、賃金水準は大きな要素である。自由主義経済では、基本的に商品やサービスの付加価値が大きくなれば労働者の賃金は増える。一方で、労働者への分配が公定価格になっている医療や福祉の分野は、労働の成果と賃金が連動しにくい。公定価格は事業所の収益は増えない仕組みであるが、これが増えないと労働者の賃金も増えない。地方から国へ意見を出していく必要がある。
○山下健康人材確保対策課長 公定価格が実勢に追いついていないことは、コロナ禍でも問題となった。今般の国の経済対策では保育士や介護士等の処遇改善の観点も含まれており、実態を検証したうえで国へ要望していきたい。
○吉田議員 クリティカル・マスの視点では、出席者の3割を占めれば意見が届くと言われている。懇話会の委員構成は男性が多いようであるが、ジェンダーを重視する観点ではどうなのか。
○山下課長 委員は商工団体を代表する人が中心で、年齢の高い男性が多くなっている。懇話会や政策企画雇用経済観光常任委員会でも指摘があり、2回目以降は代表者のみでなく現場の女性にも出席してもらう予定である。12月13日の2回目の懇話会では女性が3名追加出席される。
○吉田議員 今回は人材確保の方針であり、労働市場を対象にしている形であるが、育児、介護など労働以外の時間を大切にする観点もあったほうが、労働者に寄り添った方針になると思うがどうか。
○小見山部長 働きやすい環境は男性、女性、誰にとっても大事で、企業の経営者層の意識の問題もあるがそのような職場づくりが大事である。ジェンダーギャップの解消など様々なものに総合的に取り組むことが人材確保につながると考えている。
○吉田議員 若者の公務員離れと言われるが、社会のいろいろなものが若者から離れていっているのは、若者の意向に合っていないからと思う。高校生、大学生の話も聞いたそうだが、その部分は強めてほしいと思う。国民健康保険加入の若い世代では、精神疾患での受診が多くなっているようである。精神的なハラスメントを受けて退職等につながってしまう場合も想定されるが、若い世代の退職につながってしまうような職場での困難さについての議論はあったか。
○世古次長 ハラスメントと言うよりは職場の課題での議論はあった。カスタマーハラスメントも含めて県庁全体でハラスメント対策に取り組もうとしており、話し合われた課題等はしっかり収集、反映させ、懇話会へフィードバックしたいと考えている。
○吉田議員 資料2の8ページで、「三重県で就職すると奨学金の返済を肩代わりしてくれる」に下線がついているが、労働が大変で、返還が終わると仕事をやめてしまう人もいる。未来の選択肢を借金の担保にとられているようにも見える。三重県の奨学金返還支援の条件は4年間から8年間住むこととなっているが、個人の選択を狭めないほうが若者が離れないと思うが。
○山下課長 本県の奨学金返還の支援は、若者の県内定着を目的に、県内に一定期間住んでもらうことを条件としている。県のみでなく企業の応援も得て、若者への支援を拡充していきたい。
○吉田議員 私も若者が三重県に定着してもらったらいいと思っており、若者の声を政策に反映してほしい。
○芳野議員 民間ではリファラル採用とかアルムナイ採用という考え方がある。前者は在職職員が友人等を連れてきて採用するものだが、この場合は職場環境が成否に関わると思う。後者は一旦退職した職員の復職であり、退職した職員へ企業の案内書類を送り続ける例もある。
他県の県庁職員だった女性が結婚を機に三重県に移り住んだものの、公務職場でなく民間で働いている事例があるが、このような人を対象にするのも後者の一種と思うし、潜在保育士、看護士の掘り起こしも同じと思う。このような先進事例の紹介を行ったらどうか。
○松下部長 そのような採用の事例は体系的には把握していないが、よく聞かれる話である。外国人の場合、同じ国の職員がいると就労しやすいという事例は聞いている。
○芳野議員 ベトナム人のコミュニティから労働者を引っ張ってくる事例は聞いている。 このような成功事例を企業へ紹介するような議論も検討してほしい。
○山崎議員 中小企業、小規模企業の70%は赤字経営と言われるが、それでも採用する必要がある。企業が選ばれる条件としては、保育にかかる環境が大きい。四日市市では0歳から1歳児の保育受け入れがほとんどなく、あっても5人の枠に1000人が応募といった感じである。保育所以外は費用面、時間面の負担が大きく、このような状況では働く意思はあっても働けない。子供の預け先があっての労働であるが、県としても努力してほしい。
○世古千浪子どもの育ち支援課長 四日市市でも待機児童数が多く、子どもを預けられなくて働けない事例は多いと考えられる。県としても保育士の確保に努めているが、人材の掘り起こしも難しく、依然不足している状況である。保育士の確保は今回の方針にも記載しており、引き続き努力していく。
○山崎議員 議員として県民から預け先確保を依頼されることが多く、苦慮している。県としても努力をお願いする。
○一見知事 困難で大きな課題である。国の人口問題担当の山崎内閣官房参与の話では、1歳児、2歳児は保育の人手が多くかかるが、北欧、ドイツ、フランスでは、この年齢は父親も含めて育児休業をとった親が担うという考え方をとっているようである。この場合、育児休業がとれるような職場の対応が必要であるが、日本はそのレベルに達していない。医療、介護の公定価格の話があったが、保育士の賃金についても国で検討すべき課題であり、県から引き続き働きかける。潜在保育士の掘り起こしについては、登録制度を設けた自治体もあるようだが、市町単独でできない場合は県の支援も必要となる。中期的なものと短期的なものに分けて議論していく必要がある。
○日沖議員 この方針の進行管理は、モニタリング指標の実績確認をしていくとのことだが、議会への報告はどのように行うのか。
○山下課長 PDCAサイクルは大事であり、モニタリング指標の実績や新たな課題等は毎年度の県政レポートの中で報告する。
○日沖議員 指標の現状値がどのようになっているか報告されるのか。
○山下課長 そのとおりである。
○喜田議員 適正な賃金水準の重要性については、先日の私の一般質問では雇用経済部長の答弁があり、9月の今井議員の一般質問では総務部長の答弁があった。また、人材確保対策面でも重要との政策企画部長の答弁があったが、公契約の実態としては十分な賃金水準で支払われていないと思われる。地方自治法には最小の経費で最大の効果との条文があるが、賃金を削って達成するという意味ではない。公契約において国が示している積算単価よりもかなり低い賃金が支払われている実態を、人材確保の観点から県として一考してほしい。
○田中(智)議員 解雇規制の緩和などの動きもあり、労働市場の流動化の流れがあるが、この方針における考え方はどうなるか。
○山下課長 労働への意識が変化しており、労働市場の流動化は認識しているが、これをチャンスと捉え、転職の際には三重県へ来てもらうよう、県の魅力など有益な情報を発信していく。
○田中(智)議員 男性の育児参画の推進とあるが、育児のみでなく家事全般への参画にも着目してほしい。
○世古次長 仕事と家事の両立支援は男女に関わらず取り組むべき対策であり、人口減少対策にも寄与するものである。
○中嶋議員 方針の期間を令和7年から10年の4年間としている理由は何か。また、生成AIやロボットの影響でなくなっていく仕事もあるが、労働力の移動支援の必要性はどうか。さらに、県北部と県南部の産業構造等の違いに着目して、この方針をエリア別で作成する考えはないか。
○山下課長 県政の大本である強じんな美し国ビジョンみえは令和14年度まで、中期計画のみえ元気プランは令和8年度までとなっており、整合性は意識するものの、労働力不足は喫緊の課題であり、まずは4年間頑張ってみることとした。生成AI等の影響の対策は、リスキリングになると思うが、懇話会では県内高等教育機関でのリカレント教育の活用の意見が出ている。
○世古次長 エリア別の議論はあったが、産業構造の違いは意識しつつもエリア別の方針とすることは検討していない。
○山下課長 地域特有の課題に応じて、方針に書き込むこととしている。
○中嶋議員 外国人労働者の住居として県、市町の公営住宅の開放が必要と思うので、方針に記載はないようだが、引き続きの検討を要望しておく。