保環研年報 第26号(2024)
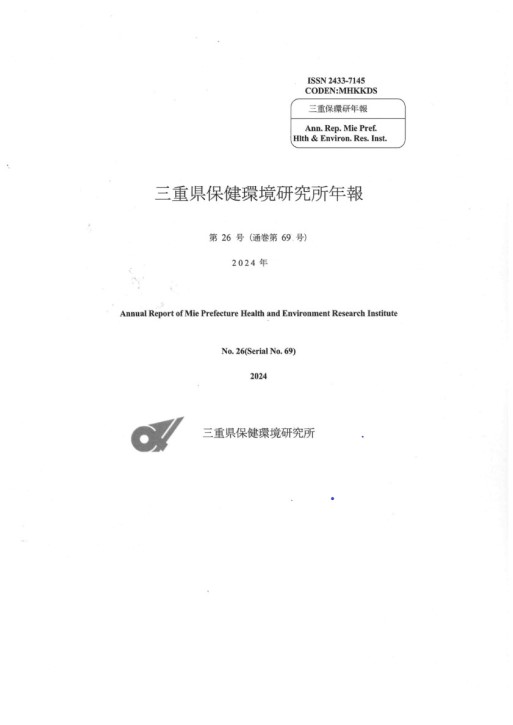 |
三重県保健環境研究所年報 第26号(通巻第69号)(2024)を発行しましたのでその概要をご紹介します。
各研究報告(原著、ノートおよび資料)の全文(PDF形式)をご希望の方は、こちらからダウンロードできます。 |
研究報告
ノート
・2024rep1 三重県における季節性インフルエンザウイルスのHemagglutinin遺伝子系統樹解析(2023/24シーズン)
矢野拓弥,川合秀弘,下尾貴宏
キーワード:季節性インフルエンザウイルス,2023/24シーズン,遺伝子系統樹解析,
三重県感染症発生動向調査事業
三重県感染症発生動向調査事業において2023/24シーズン(2023年第36週~2024年第35週)の季節性インフルエンザウイルスの流行は,A/H1N1pdm09インフルエンザウイルス,A/H3N2インフルエンザウイルスに加えて,B型インフルエンザウイルス(ビクトリア系統)が4シーズンぶりに流行がみられ,3種の亜型による流行像であった.2023/24シーズンの季節性インフルエンザウイルスについてHemagglutinin(HA)遺伝子の系統樹解析を実施しSubclade分類を行った.A/H1N1pdm09インフルエンザウイルスは多くがSubclade D.2であり流行期の前半(2023年9月~2024年1月)に主に検出された.A/H3N2インフルエンザウイルスは,Subclade J.1が主流であり,流行期の前半の2023年9月~2024年2月に多く検出された.B型インフルエンザウイルス(ビクトリア系統)はSubclade C.5,C.5.1,C.5.6,C.5.7が検出されたが,僅差ではあるがC.5.1が最も多く,2023年11月~2024年4月の間に検出され,複数のC.5の派生株(C.5.1,C.5.6,C.5.7等)が混在流行し,多様化の傾向がみられた.
・2024rep2 抗インフルエンザ薬バロキサビル マルボキシルにおける耐性変異を有する季節性インフルエンザウイルスの動向把握-三重県(2019年5月~2024年10月)
矢野拓弥,川合秀弘,下尾貴宏
キーワード:抗インフルエンザ薬,バロキサビル マルボキシル,薬剤感受性試験,
抗インフルエンザ薬耐性株サーベイランス,耐性変異
2019年5月から2024年10月までに三重県感染症発生動向調査事業において分離・検出されたA/H1N1pdm09インフルエンザウイルス(63件)およびA/H3N2インフルエンザウイルス(94件)およびB型インフルエンザウイルス(ビクトリア系統)(48件)について,抗インフルエンザ薬であるバロキサビル マルボキシルに対する耐性変異の指標であるPolymerase acidic subunit(PA)遺伝子のアミノ酸配列解析を実施した.調査期間中のバロキサビル マルボキシル耐性変異の検出状況は,A/H1N1pdm09ウイルスは63件中1件(1.6%),A/H3N2ウイルスは94件中1件(1.1%)から本薬剤の耐性変異が確認され,この2例は本薬剤未投与の患者から検出された事例であった.またA/H1N1pdm09ウイルスは,バロキサビル耐性変異のPA(I38T)
耐性変異を有するウイルスであった.一方でA/H3N2ウイルスは,異なるアミノ酸によるPA(I38V)耐性変異を獲得していた.
・2024rep3 急性呼吸器感染症における遺伝子組換え型アデノウイルスの動向(2023年~2024年3月)-三重県
矢野拓弥,川合秀弘,下尾貴宏
キーワード:三重県感染症発生動向調査事業,アデノウイルス,遺伝子組換え型,
急性呼吸器感染症,Hexon,Penton base,Fiber
三重県感染症発生動向調査事業において,2023年1月~2024年3月の間に県内の医療機関を受診し,急性呼吸器症状を呈した患者から採取した呼吸器由来の臨床検体を用いて検出されたアデノウイルス(AdV)について遺伝子組換え型AdVの動向を調査した.調査期間中に検出されたAdVの遺伝子であるHexon,Penton base,Fiberを用いて遺伝子系統樹解析による遺伝子組換え型AdVの検索を実施した.検出された遺伝子組換え型AdVは89型1件と108型4件,さらにAdV 5型と89型の新規の遺伝子組換え型AdVが1件検出された.
・2024rep4 A/H3N2インフルエンザウイルスにおけるHemagglutinin遺伝子解析によるSubclade分類について(2014/15~2022/23シーズン)-三重県
矢野拓弥,川合秀弘,下尾貴宏
キーワード:A/H3N2インフルエンザウイルス,Hemagglutinin(HA),
Subclade分類,遺伝子系統樹解析,アミノ酸変異
三重県内において2014/15~2022/23シーズンに分離・検出されたA/H3N2インフルエンザウイルス(A/H3N2ウイルス)について,Hemagglutinin(HA)遺伝子系統樹解析によるSubclade 分類を実施した.今回の調査で,A/H3N2ウイルスは遺伝子的に多様化が進み, 3~4シーズン内で複数の異なるSubcladeによる集団を形成し,その中から派生したウイルスが,次の流行へとシフトする傾向がみられた.インフルエンザウイルスのワクチン株との抗原性状の差違,あるいは新たなSubcladeに属する流行ウイルスの出現傾向を捉えることは,感染拡大防止の予防啓発等のインフルエンザ予防対策に活用が可能である.このことは高齢者等への重症化予防策の1つであるワクチン接種の方向性を明示でき,県内の医療体制の連携強化および先進的な感染予防対策の推進に繋がることが期待される.
・2024rep5 三重県における農産物中の残留農薬検査について(2012年度~2023年度)
原 有紀,内山恵美,勝矢晃治,渡部ひとみ,豊田真由美,吉村英基
キーワード:残留農薬,一斉分析法,食品衛生法,ポジティブリスト制度
当研究所ではこれまでに農産物中の残留農薬迅速系統分析法を開発し,さらにこの方法を行政検査に適用して農産物中の残留農薬検査を行ってきた.三重県内に流通している農産物の農薬残留実態を把握し,より効果的な食品監視を行う目的で,過去12年分の検査結果について整理した.検査を実施した735検体のうち142検体から残留農薬が検出された(検出率19.3%).こまつな,ねぎからシペルメトリン,ほうれんそうからフルフェノクスロン,かんきつ類果実からメチダチオンの検出が多かった.残留基準を超過した農産物は,735検体中2検体であった(違反率0.3%).
・2024rep6 大豆加工食品中の遺伝子組換えDNA検査におけるPCR装置の同等性確認試験
𠮷田真平,中野陽子,原 有紀,内山恵美,吉村英基
キーワード:大豆,遺伝子組換え食品,リアルタイムPCR,同等性確認試験,RR2
わが国における遺伝子組換え食品の表示については,大豆等の農産物およびこれらの加工食品が対象となっている.遺伝子組換え食品の表示が適正であるかについては,「安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法(以下,「公定法」)」にて科学的に検証する方法が示されており,リアルタイムPCRによるDNA検査法が基本となっている.大豆加工食品中のDNA検査に用いられるPCR装置として,公定法には代表的なものが示されているが,これら以外の装置についても,従来装置との同等性が確認されれば,検査での使用が認められている.本研究では,PCR装置Quant Studio®5と,公定法で既に使用が認められているABI PRISM®7900との同等性確認試験を行った.この結果,QuantStudio®5はABI PRISM®7900との同等性が確認され,大豆加工食品のDNA検査に適用可能であると考えられた.
・2024rep7 三重県産生鮮魚類の水銀調査(2004年度~2024年度)
𠮷田真平,吉村英基,勝矢晃治,内山恵美,川合秀弘,佐藤洋之,下尾貴宏
キーワード:水銀,魚類,クロダイ,伊勢湾,妊婦
魚介類中の水銀濃度について,暫定的規制値が設けられているため,三重県は県内で流通する生鮮魚類の検査を行っている.本報告では,三重県内で流通する生鮮魚類の水銀検出傾向を明らかとするため,2004年度から2024年度に得た34魚種79検体の試料における水銀検査結果を取りまとめ,考察を行った.
魚種毎の総水銀濃度は,33魚種77検体で0.4ppm(暫定的規制値の目安)以下であったが,クロダイ(Acanthopagrus schlegelii)およびマハタ(Epinephelus septemfasciatus)の各1検体は,0.4ppmを超過していた.一方,メチル水銀濃度では,クロダイ(総水銀0.47ppm)およびマハタ(総水銀0.46ppm)で,それぞれ0.24ppmおよび0.19ppmであった.また,検体数が3以上ある魚種(9魚種)に限定すると,総水銀濃度の平均値が最も高い魚はクロダイであり,0.23ppmであった.今回の結果から,検査対象となった34魚種79検体について,暫定的規制値を超過する魚種は流通していなかったものの,伊勢湾におけるクロダイの総水銀の検出値は,上昇傾向にあるため,伊勢湾産クロダイの水銀の由来には注視が必要と考えられる.特に胎児は血液脳関門の発達が不十分であり,妊婦の魚食の参考資料とするため,魚食の際の水銀濃度について,基礎データの蓄積が必要であると考えられた.
・2024rep8 三重県産生鮮魚類のPCB調査(2004年度~2024年度)
𠮷田真平,吉村英基,勝矢晃治,内山恵美,川合秀弘,佐藤洋之,下尾貴宏
キーワード:PCB,魚類,化審法,伊勢湾,熊野灘
魚介類中のPCB濃度について,暫定的規制値が設けられているため,三重県は県内で流通する生鮮魚類の検査を行っている.本報告では,三重県内で流通する生鮮魚類の近年のPCB検出傾向を明らかとするため,2004年度から2024年度に得た34魚種79検体の試料におけるPCB検査結果を取りまとめ,考察を行った.
魚種毎のPCB濃度は,34魚種79検体でいずれも暫定的規制値以下であり,34魚種中25魚種が検出限界値(0.01ppm)未満であった.また,2004年度から2024年度までの生鮮魚類のPCB濃度の平均値は,全ての年度で0.01ppm以下であり,1970年代の平均値と比べ著しく低下していた.調査の結果,三重県産生鮮魚類におけるPCB濃度は,少なくとも2004年度以降は検出限界値(0.01ppm)付近で維持しており,三重県においては,暫定的規制値を超過する魚類が水揚げおよび流通する可能性は低く,一般的な食生活の中での魚食を通じたPCBによる健康被害の発生の懸念は少ないと考えられた.
・2024rep9 マルチベネフィットの視点でとらえた土壁材の再生製品開発に向けた基礎研究
近藤笑加,今村一貴*,柘植 亮,森 理佳,矢野真弓,石田健太**,山川雅弘
キーワード:土壁材,乾式選別,湿式選別,焼成,全有機体炭素
土壁材の再資源化を最終的な目標として,解体工事現場で排出された壁土や屋根土に含まれる藁などの有機物を除去するための効果的な処理方法を実験的に検討した.
乾式選別処理と湿式選別処理,焼成処理の3方法を5種類の土壁材にそれぞれ施し,土壁材中の有機物量と,溶出量試験における溶出水の有機物濃度等を測定してその変化量を調査するとともに,土壌との比較を行った.
乾式選別処理では,土壁材中の有機物除去には目開き1 mmまたは0.25 mmの篩による選別が効果的であったが,溶出水中の有機物濃度は処理をしても大きな変化はみられず,目開きが最も小さい0.25 mm篩では有機物濃度が増加する結果であった.湿式選別処理では有機物除去効果が低く,処理に伴って排出された洗浄水の有機物濃度も比較的高値で検出された.焼成処理は土壁材中の有機物量が有機物除去に最も効果的な処理方法であったが,処理後の土壁材の溶出量試験においてCr(Ⅵ)やAs等の有害物質が土壌の汚染に係る環境基準値を超過した.乾式選別処理,湿式選別処理後の土壁材を土壌と比較したところ,土壁材に含有する有機物量は処理前であっても土壌と同程度または少なかったが,溶出水中の有機物濃度は土壌より高値であった.
有機物を除去するための効果的な処理方法は,エネルギー使用量,二酸化炭素排出量,設備投資コスト等の視点から目開き1 mmの篩による乾式選別処理と考えられたが,処理をしても土壌と比較して水溶性の有機物が多く,再資源化にあたって課題があった.
・2024rep10 再生品の環境安全性に関する調査研究-改良土・再生土-
近藤笑加,山川雅弘,今村一貴,柘植 亮,森 理佳,矢野真弓,石田健太
キーワード:改良土,再生土,建設汚泥,固化材,環境安全性,製造管理体制
建設汚泥等の産業廃棄物に固化材を添加して製造された改良土・再生土の安全性に関する現状確認のため,三重県内の産業廃棄物中間処理業者6者に製造に関する管理体制のヒアリング調査を実施した.あわせて,処理を受託した産業廃棄物や原材料,固化材等の改良土・再生土の製造に使用するすべてと,製造した改良土・再生土,計22試料を採取し,土壌溶出量試験,環境最大溶出可能量試験等を実施した.
ヒアリング調査の結果,調査を実施した事業者6者すべてが土壌の汚染に係る環境基準値を改良土・再生土の自主管理基準値として設定し,改良土・再生土の安全性を確認していた.また事業者3者は産業廃棄物の受入時に自主検査を実施していた.
土壌溶出量試験の結果,改良土・再生土は土壌の汚染に係る環境基準を満たしていたが,一部の固化材は鉛と六価クロムの土壌の汚染に係る環境基準を超過した.土壌含有量試験の結果,多くの試料で鉛が検出されたものの,土壌含有量基準を満たしていた.環境最大溶出可能量試験の結果,土壌溶出量試験と土壌含有量試験において検出されなかったカドミウムが,酸性環境下で溶出する可能性があることが判明した.
資料
・2024rep11 2023年感染症発生動向調査結果
楠原 一,小林章人,矢野拓弥,川合秀弘
キーワード:感染症発生動向調査事業,病原体定点医療機関,インフルエンザ,
感染性胃腸炎,日本紅斑熱,新型コロナウイルス
感染症発生動向調査事業の目的は,医療機関の協力を得て,感染症の患者発生状況を把握し,病原体検索により当該感染症を微生物学的に決定することで流行の早期発見や患者の早期治療に資することにある.また,感染症に関する様々な情報を収集・提供するとともに,積極的疫学調査を実施することにより,感染症のまん延を未然に防止することにもある.
三重県では,1979年から40年以上にわたって本事業を続けてきた.その間,検査技術の進歩に伴い,病原体の検出に必要なウイルス分離や同定を主としたウイルス学的検査,さらに血清学的検査に加えてPCR法等の遺伝子検査やDNAシークエンス解析を導入し,検査精度の向上を図ってきた.また,検査患者数の増加により多くのデータが蓄積されてきた結果,様々な疾患で新たなウイルスや多様性に富んだ血清型,遺伝子型を持つウイルスの存在が明らかになってきた1~3).
以下に2023年の感染症発生動向調査対象疾患の定点医療機関等で採取された検体について,病原体検査状況を報告する.
・2024rep12 2023年度感染症流行予測調査結果(日本脳炎,インフルエンザ,風疹,麻疹)の概要
矢野拓弥,楠原 一,小林章人,川合秀弘,下尾貴宏
キーワード:感染症流行予測調査,日本脳炎,インフルエンザ,風疹,麻疹
本調査は1962年に「伝染病流行予測調査事業」として開始された.その目的は集団免疫の現状把握および病原体の検索等を行い,各種疫学資料と併せて検討することによって,予防接種事業の効果的な運用を図り,さらに長期的視野に立ち総合的に疾病の流行を予測することである.その後,1999年4月「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の施行に伴い,現在の「感染症流行予測調査事業」へと名称変更された.ワクチンによる予防可能疾患の免疫保有調査を行う「感受性調査」およびヒトへの感染源となる動物の病原体保有を調査する「感染源調査」を国立感染症研究所および県内関係機関との密接な連携のもとに実施している.これまでの本県の調査で,晩秋から初冬に日本脳炎ウイルス(JEV)に対する直近の感染を知る指標である2-メルカプトエタノール(2-ME)感受性抗体が出現1)したことなど興味深い現象が確認されてきた.また,以前は伝染病流行予測調査事業内で実施されていたインフルエンザウイルス調査において,1993/94シーズンに分離されたインフルエンザウイルスB型(B/三重/1/93株)が,ワクチン株に採用された等の実績がある.ヒトの感染症における免疫状態は,各個人,地域等,さまざまな要因で年毎に異なるため,毎年の感染症流行予測調査事業における血清収集は重要である.集団免疫の現状把握と予防接種事業の促進等,長期的な調査は感染症対策には不可欠であり,本調査のような主要疾患についての免疫状態を知る上で,継続的な調査は,感染症の蔓延を防ぐための予防対策として必要性は高い.以下に,2023年度の感染症流行予測調査(日本脳炎,インフルエンザ,風疹,麻疹)の結果について報告する.
・2024rep13 SARS-CoV-2(オミクロン株)のゲノム分子疫学解析(2023年11月~2024年11月)-三重県-
矢野拓弥,川合秀弘,下尾貴宏
キーワード:新型コロナウイルス,COVID-19,SARS-CoV-2,ゲノムサーベイランス,
オミクロン株,組換え体
2019年12月に中国(武漢市)から罹患者が多数報告されたSevere Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2(SARS-CoV-2)を起因とする新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は,2020年1月以降, SARS-CoV-2が国内へ流入し感染拡大1~3)に至った.本県においては2020年1月下旬に県内で初めてSARS-CoV-2陽性者が確認され4),その後,世界的な流行5~7)となり現在に至っている.
我が国ではCOVID-19の流行が始まった2020年当初より,SARS-CoV-2の感染拡大抑制対策の1つとして,行政検査の陽性検体を活用したゲノムサーベイランス体制が構築され,感染クラスターに特有な遺伝子情報やそのクラスター間の共通性の解析8)が実施されてきた.
本県においても,このゲノムサーベイランスの分子疫学解析結果から,2020年の第1波からのこれまでの流行波に関与したSARS-CoV-2系統とそのウイルスゲノムの特徴および変遷を明らかにしてきた9-12).
一方でCOVID-19は2023年5月に感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更され,同時に従来の行政検査でSARS-CoV-2陽性となった患者の臨床検体を用いたゲノムサーベイランス体制から,今後のSARS-CoV-2変異種の出現に備えることを目的とし,COVID-19ゲノム解析のために検体採取を行う定点医療機関を定め,新たな体制で三重県新型コロナウイルス感染症ゲノムサーベイランスとして継続されている.昨年度は第8波と第9波の本県における流行系統や組換え体に関する検出報告の詳細を報告13)したが, その後の2023年11月以降に当所において検出されたSARS-CoV-2(オミクロン株)について,次世代シーケンサー(Next Generation Sequencer;NGS)を用いてゲノム分子疫学解析を実施し,流行ウイルスのゲノム系統に関する動向監視を実施したので以下に報告する.
・2024rep14 三重県における2023年度環境放射能調査結果
谷本健吾,佐藤大輝,吉村英基
キーワード:環境放射能,核種分析,全ベータ放射能,空間放射線量率
日本における環境放射能調査は,1954年のビキニ環礁での核実験を契機に開始され,1961年から再開された米ソ大気圏内核実験,1979年スリーマイル島原発事故,1986年チェルノブイリ原発事故を経て,原子力関係施設等からの影響の有無などの正確な評価を可能とするため,現在では全都道府県で環境放射能水準調査が実施されている1).
三重県は1988年度から同事業を受託し,降水の全ベータ放射能測定,環境試料および食品試料のガンマ線核種分析ならびにモニタリングポスト等による空間放射線量率測定を行って県内の環境放射能のレベルの把握に努めている.
さらに福島第一原子力発電所事故後は,国のモニタリング調整会議が策定した「総合モニタリング計画」2) に基づき原子力規制庁が実施する調査の一部もあわせて行っている.
本報では,2023年度に実施した調査の結果について報告する.
・2024rep15 三重県内の家屋解体工事で発生する土壁材の処理実態調査結果
近藤笑加,今村一貴,山川雅弘
キーワード:土壁材,処理実態調査,再資源化
家屋解体工事に伴って発生する土壁材の多くは建設系廃棄物として処理されている.土壁材は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)の特定建設資材に該当しないため再資源化されにくく,処理費用が高額となることを背景に,不適正な処理がなされる場合がある1,2).この場合,土壁材は土に藁,すさ,糊などの有機物を含んでいることから,有機性汚濁水や硫化水素が発生し周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性がある3).
また,土壁材は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)で管理型産業廃棄物に分類される.石膏ボード等のボード類に付着した土壁材は,石膏ボードと土壁材の分離が困難である場合が多く,埋立処分量の増加が懸念される.
そこで,三重県内の家屋解体工事現場で発生する土壁材の処理の実態や課題を把握することを目的にアンケート調査を実施したので,その結果を報告する.
・2024rep16 三重県における光化学オキシダントの挙動に対する窒素酸化物の影響
西川 奈緒美,佐藤 邦彦,小河 大樹,井原 篤人,寺本 佳宏,川合 啓之
キーワード:光化学オキシダント,窒素酸化物,パッシブ法,自動車交通量
NOタイトレーション効果,水平分布図
我が国では高度経済成長期に工場・事業場からの排ガスに含まれるばい煙等により,四日市ぜんそくに代表される深刻な健康被害が発生し,大気汚染が社会問題となった.また,微小粒子状物質(PM2.5)および光化学オキシダント(Ox)による大気汚染も問題となっており,様々な健康影響が懸念されている1).これらの大気汚染物質は,短期ばく露や長期ばく露による呼吸器系への影響などの健康影響を考慮して大気汚染に係る環境基準が設定されており,近年,様々な大気汚染防止対策の効果により多くの項目で改善傾向が見られ,高い環境基準達成率を示している2).
しかし,環境基準項目の一つであるOxは,日本全国のほとんどの地域で環境基準を達成できていないのが現状である3).
三重県においても,大気汚染防止法や自動車NOx・PM法などの法規制等により,前駆物質であるNOxや揮発性有機化合物(VOC)の濃度は減少しているが,三重県内大気環境測定局(測定局)のうちOxを測定している一般環境測定局(一般局)23局すべてでOxは環境基準を達成していない.また,緊急時の措置(予報,注意報)を発令する高濃度事象が毎年のように発生しており,発令地域の広域化も見られている4).
Oxの主成分はオゾン(O3)であり,太陽光を受けて大気中のNOxや炭化水素が光化学反応を起こし,アルデヒド等の化学物質とともに生成される.Oxが発生すると目や喉の痛み,ぜんそくの発作等を誘発し健康被害を生じさせるおそれがある.
一方,NOxは高温で物質が燃焼する際に発生する窒素酸化物の総称であり,そのうち一酸化窒素(NO)と二酸化窒素(NO2)は,自動車排ガスに多く含まれている.NO,NO2およびO3は,
NO2 + O2 ⇔ NO + O3
で表される化学平衡が成立しており, NOxはO3の生成と消滅に深く関わっているため,Oxの挙動において影響を与えると考えられている.特にこの反応のうち,「 NO + O3 → NO2 + O2 」の反応では,NOはO3と反応してNO2とO2になるため,オゾンを減少させる効果があり,「NOタイトレーション効果」と呼ばれている5).
三重県内の自動車排ガス測定局(自排局)8局では,NOx,NOの測定は行っているもののOxの測定を行っていないため,自動車排ガスによるNOxとOxの関係は明らかになっていない.
そこで,本研究でOxの生成における原因物質の一つであるNOxを排出する自動車に着目し,排ガスの影響が大きい沿道において,ポンプなどの機器を使用せず,拡散原理により試料を捕集する「パッシブ法」6)による実態調査を行い,NOxや Oxの濃度変化等を調べるとともに,実態調査で得られたデータをもとに,NOxと自動車交通量の関係性を検討した.
また,実態調査と一般局のデータを比較し,パッシブ法で得られたOx等のデータを,補完的に自排局のデータと組み合わせて活用できないかについて検討した.
次に,測定局のNOxおよびOxのデータを用いて,各項目における経年変化等を調査するとともに,Ox濃度の変動の要因を把握するため, NO がO3と反応し NO2と O2になり,O3を減少させる反応を加味した指標である,ポテンシャルオゾン(PO)を用いて検討した.
さらに,伊勢湾を含めた三重県周辺におけるOxの挙動を把握するため,NOxおよびOxの時間変化等について,濃度の水平分布図を用いて解析を行ったので報告する.