三重県水産研究に100年(創立百周年記念誌)
三重県水産試験場・水産技術センターにおける研究史のトピックス
9.イカナゴ資源管理に関する研究
伊勢湾の船曳網(バッチ網)漁業は昭和11年(1936年)頃、徳島県から導入され、イワシ類を対象として最盛期には三重県船で約100統が操業していた。その後小型船曳網(トウガラシ網)漁法も加わり、夏期はイワシ類、冬期はイカナゴを漁獲するのが年間の操業パターンで現在でも変化はない。イカナゴの漁期は1月解禁の親魚漁(産卵後の親魚)と春3月解禁する新仔漁(12~1月生まれのシラス~未成魚が漁獲対象)の2回ある。
イカナゴ資源に関する研究は昭和25年(1950年)、漁獲制限および不漁原因究明の基礎資料を得ることを目的として、国立水産研究所の全国イワシ魚体調査に準じて開始された。調査内容は体長、体重、肥満度、脊椎骨数の生物調査および漁獲量等漁業実態調査である。これらの調査により漁獲の豊凶は当才魚の資源量によることが分かり、産卵生態等の親魚調査も重点的に行うこととなった。昭和32年(1957年)には、産卵期が12月中旬から2月上旬で、盛期は1月上旬であること、主産卵場は伊勢湾口の砂または砂貝穀質の場所であること、孵化した稚仔は潮流によって湾内に運ばれ、成長に従い湾中央部に移動することが判明した。昭和33年の春漁期は、親魚漁が豊漁であったのに対し新仔漁は不漁に終わり、その原因として親魚による稚仔の捕食が考えられた。昭和34年の漁況も前年同様の結果となり、親魚胃内容物調査によって、親魚の稚仔捕食が大きく影響していることが確認された。昭和35年(1960年)からは漁況予報を試みることとし、これまでの研究で得られた知見である、昭和26年~34年の9ケ年間の11、12月の降水量と翌春の当才魚漁獲量の間には極めて高い負の相関関係があること、稚仔の体長組成の幅が広いと豊漁であることを基本として、産卵期の湾口部の水温や卵・稚仔の分布量の調査結果を総合的に考察して漁獲量を予報することとした。この間漁法も次第に改良され中でも200kc魚群探知機の導入は新仔(特にシラス)の漁獲を飛躍的に増大させた。従来イカナゴは常時海底付近を遊泳するものと考えられていたが、同魚探の導入によって新仔は表中層を遊泳することが判明し、漁具を遊泳層に合わせて曳網する現在の漁法が確立した。このような漁法の効率化に加え湾口部の親魚漁に船曳網が許可されたことから資源量は急激に減少した。
昭和51年(1976年)、これまでの方法では予報精度の向上は困難であると考え、新しい手法の開発に着手した。今後の予報には生物情報を取り入れることが重要と判断し、過去の生物データを全て整理し解析を試みた。新仔漁期間の成長が直線式に適合することを応用し、成長式と漁獲量から日別(旬別)の漁獲尾数が推定された。さらにこれらの値からデリュリー法によって加入資源量の推定が可能となった。これらのデータに基づく資源診断の結果、新仔の漁獲率は95%にも達していて再生産に必要な親魚量が不足していることが明らかとなった。また、昭和52年から再生産機構の解明に取り組み、この年には魚体長と抱卵数との関係式や親魚は殆ど1年魚で構成されていることを、翌53年には産卵期の水温と成熟度の関係や産卵期間の長さに関する影響要因を解明した。さらに、過去15年間の親魚尾数-加入尾数データから伊勢湾産イカナゴの再生産関係には次頁の図に示すリッカー型再生産曲線がよく適合することがわかった。
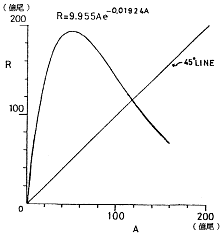
伊勢湾産イカナゴ再生産曲線(リッカ一型)
以後この曲線を使って漁況予報を行うとともに、漁業者説明会において資源状態と最大持続生産量(MSY)の概念(漁期末に獲り残すべき資源尾数)について指導した。この再生産曲線は、その後イカナゴ資源管理が現在のように全国的に評価される端緒となった。
以上のように、資源管理の科学的裏付けが得られたが、容易に漁業者には受け入れられず、資源の回復は進まなかった。そこで産卵親魚を保護する目的で、親魚の漁獲規制を図った。まず、親イカナゴ船曳網漁業許可内容を変更し、漁期開始を11月1日から12月1日とした。さらに翌年からは産卵前の親魚を禁漁とし、親魚漁の試験曳き制度を設け、水産試験場の研究員が産卵状況を確認し、その結果を踏まえて、漁政課が解禁日を設定した。このように科学的データに行政が即応してくれたことがその後の好結果を生むことにもなった。
当初「今年伊勢湾内にイカナゴが100億尾いる」と説明したら爆笑をかった。今では年が明けると「今年のイカナゴは何億尾か」という問い合わせが漁業者は勿論加工業者からもくるほどイカナゴ資源管理には漁獲重量(トン)よりも漁獲尾数が重要であることが業界に浸透した。
昭和53年(1978年)は大不漁となった。このため、翌54年伊勢湾水産試験場は再生産曲線と前年の生残魚(親魚量)から初期資源尾数は、30億尾程度とみて大不漁の予報を発表し、その初期資源尾数を全て翌年の親魚とすれば来年以降資源回復が図れると考え、解禁取り止めを指導した。しかし、漁業者は春一番の期待の漁であることから解禁はしたものの実質1日で終漁の形となり、この時点で伊勢湾水産試験場の漁況予報が初めて漁業者に認められた。この年が伊勢湾産イカナゴ資源管理元年といえる。昭和56年(1981年)日本水産学会漁業懇話会で伊勢湾産イカナゴについて、親魚量は最低10億尾が必要と発表した。こうした一連の研究成果が昭和58年頃から現われ始め資源は徐々に回復していった。
平成2年(1990年)から愛知県水産試験場との連携のもと、広域資源培養管理対策推進事業が実施され、イカナゴの再生産機構に関する多くの知見が得られ、再生産型資源管理のさらなる理論化が進められた。天然海域では伊勢湾産イカナゴの夏眠場所が特定され、1年の約半分を過ごす夏眠期の生態解明に大きく寄与した。また、親魚の飼育技術、卵の孵化や仔稚魚の飼育技術も確立され、飼育実験から成熟・産卵様式、再生産力(抱卵数、卵質、群成熟率等)の決定過程、発生初期の生態特性等が解明された。イカナゴ親魚が仔魚を共食いする現象についても、飼育実験や野外調査を通じて定量的評価が試みられ、再生産に及ぼす影響がきわめて大きく、リッカー型再生産関係を形成する主な要因となっていることが明らかとなった。伊勢湾産イカナゴの加入量は、基本的には親魚量によって決定されることがわかり、翌年漁期のために適切な親魚量を確保するという「再生産型資源管理」の有効性が理論的に裏付けられた。

イカナゴ夏眠魚の分布調査(愛知県と共同)
これらの科学的裏付けをもとに、三重県水産技術センター、愛知県水産試験場、三重・愛知漁業者が検討を重ね、平成4年(1992年)には資源管理指針が策定された。指針は ①産卵親魚の保護、②解禁日の設定、③終漁日の設定、④夏眠場所の保護、の4項目からなり、これを基本に両県漁業者の協力のもと、資源管理が実践されている。この資源管理方式は、伊勢湾船曳き網漁業者の経営安定に大きく寄与しているものと思われる。
伊勢湾におけるイカナゴの資源管理はその活動状況等が評価され、平成4年(1992年)全国豊かな海づくり大会において最高の賞である「全国海づくり大会会長賞」を前例のない三重・愛知両県関係漁業団体が連名で受賞するという栄誉を受けている。両県関係漁業者の中に優れたリーダーがいたことも成功した大きな要因である。