三重県水産研究に100年(創立百周年記念誌)
三重県水産試験場・水産技術センターにおける研究史のトピックス
3.魚類養殖・種苗生産に関する研究
(1) 魚類養殖
●養殖技術開発
我が国における魚類養殖は昭和2年(1927年)香川県安土池においてブリを放養したのが始まりとされており、昭和30年代までは養殖産地であった香川県や徳島県へ、ブリ養殖種苗であるモジャコのすべてを三重県で採捕し供給してきた。昭和30年頃には三重県の熊野灘沿岸地域でも採捕したモジャコの一部を網生簀に蓄養することを始めていたが、ブリの養殖は築堤式あるいは網仕切式でのみ行われており、生簀網による養殖技術は未開発であったため、長期間の蓄養はあまりうまくいかなかった。
昭和33年(1958年)には三重県水産試験場尾鷲分場では生簀網によるブリの養殖試験に取り組み、年内に約1kgにまで成長させて試験出荷し、十分採算がとれることを証明した。その後昭和35年度まで定置網の雑魚や冷凍イワシを餌料として飼育を継続し、2歳魚5、6kgまでの養殖に成功した。昭和33年に早くも生簀網によるブリ養殖技術の講習会を開催し、技術の普及に努めたため、県内外でのブリ養殖は急速に普及し、年々生産量が増大した。
一方、ブリ養殖の増加に従ってモジャコの需要量が増大し、他県でもモジャコ採捕に進出したため、全国のモジャコの採捕尾数は2,000万尾を越え、ブリ資源への影響が懸念され始めた。このため、昭和38~40年に東海区水産研究所を中核にした「モジャコ採捕のブリ資源に及ぼす影響に関する研究」が三重県を始め14県の参加を得て実施され、ブリの資源、生態について多くの知見が得られた。これらの成果は後の国によるモジャコ採捕尾数の割当制として反映されることになる。
昭和40年代までは養殖魚のほとんどをブリが占めており、尾鷲分場および尾鷲水試では給餌量、給餌回数、飼育密度、冬期の投餌法などブリ養殖技術改善のための研究を行ってきた。しかし、次第に養殖魚種拡大への要望が高まり、昭和44~46年にはマダイの養殖試験に取り組み、配合ペレットで充分養殖可能であることを明らかにした。その後、マダイは徐々に養殖量が増加したのに対して、ブリは昭和57年から減少に転じ、平成元年(1989年)にはついにマダイとブリの生産量が逆転してマダイが養殖魚の主流を占めるようになった。
マダイについてはこれまで養殖技術開発があまりなされてこなかったが、近年全国のマダイの生産量が飛躍的に増大し、供給過剰となって産地間競争が激化してきたことから、養殖マダイの品質評価の決め手ともいえる体色の改善技術に対する要望が大きくなった。そこで平成7~9年にマダイの色揚げに関する研究を行い、マダイの体色判定に色彩色差計を導入して客観的な評価を行うとともに、高品質マダイの判定基準を設定した。また、アスタキサンチンを添加した飼料で12週間飼育すると体色基準をクリアーする高品質マダイを生産できることを明らかにした。ただし、黒化要因であるメラニン色素の改善については今後の課題として残された。

色彩色差計でマダイの体色を計る
●飼料開発
昭和30年代のブリ養殖の急激な増加は定置網の雑魚等に頼っていた餌料では供給不足となり、昭和38年(1963年)から北洋フィッシュミールと生餌を練り合わせた配合飼料の開発に着手し、断続的に昭和46年(1971年)まで実施したが、実用性のある配合飼料を開発することはできなかった。
昭和50年代になると生餌ミンチによる漁場の汚染が深刻な問題となり、昭和54~56年には漁場への汚染負荷の少ない飼料としてオレゴンモイストペレットの開発研究を行い、業者に普及させることができた。その後もモイストペレットの改良研究を進めるとともに、更に汚染負荷の少ないドライペレットやエクストルーデッドペレットの導入試験を実施して業者への普及に努めた。

モイストペレット
平成年代になると養魚餌料の主体であったマイワシの漁獲量が激減したのに加えて、エルニーニョの影響でペルー産魚粉も高騰したため、平成2~9年にかけて東京水産大学と共同で、脱脂大豆粕、コーングルテンミール、ミートミール、フェザーミールなどの魚粉の代替タンパク質としての利用性について研究した。その結果、これらの代替タンパク質を50%程度魚粉と置き換えた配合飼料は、ブリおよびマダイに対して実用性のあることが明らかになった。さらに、代替油脂に関する研究も実施し、ブリ用配合飼料(あるいはドライペレット)では魚油の50%程度をヤシ油あるいは牛脂で置き換え可能であることを明らかにした。
平成8年(1966年)からは配合飼料の成分に公定規格を設定し、安心して使用できる配合飼料が普及するよう研究を進めている。
●魚病対策
昭和33年(1958年)にブリ養殖を始めた頃は魚病の問題はほとんどなかったが、養殖量が増加するにつれ寄生虫による魚病が発生するようになり、昭和38年(1963年)には三重県立大学水産学部と共著で「養殖ハマチの病気について」と題する魚病対策パンフレットを配布している。魚病が深刻な問題となったのは、昭和42年(1967年)のブリに対するノカルディア症が最初である。これ以降、魚病対策が尾鷲分場の主要業務になり、その後の類結節症の蔓延に伴って、昭和47~53年および昭和59~63年には類結節症ワクチンの開発研究を行ったが、実用化するには至らなかった。また、昭和48年にビブリオ病、昭和51~53年にイクチオフォヌス感染症、昭和58~61年に連鎖球菌症、平成2~4年にブリ上弯症、平成7~9年にハタ類の転覆病に対する研究に取り組み、種々の対策を講じてきた。昭和57年(1982年)には尾鷲分場が三重県魚病指導総合センターとして位置づけられ、魚病診断、対策指導が日常的な業務になった。
平成3年(1991年)にはマダイにイリドウィルス病が発生し、その後毎年多発したもののウィルス病への対策は無きに等しいものであった。平成7年(1995年)からイリドウィルス病対策試験を開始し、罹病後の絶食はへい死率低減効果の大きいことが確認され、イリドウィルス病への対策は消極的ながらある程度可能になった。現在はウィルス病に感染しない健康魚を作るため、養殖魚の生体防御機能の判定手法と機能向上のための養殖技術の開発を行っているところである。
●魚類養殖漁場環境
魚類養殖は投餌養殖であるため、漁場への汚染負荷は不可避であり、昭和39年(1961年)には早くも養殖漁場の汚染実態を把握するため養殖実態と漁場環境調査が行われ、同様の調査が昭和48年(1973年)まで継続実施されている。昭和50年代になると漁場環境の悪化によって生産性の低下が目立ち始めたため、昭和53年(1978年)に「三重県魚類養殖指導指針」を策定し、漁場利用に制限を加えて漁場環境保全を図ることとした。この指針は昭和61年と62年に一部改定され現在も生き続けているが、自主規制であるためあまり効果を発揮していない。その後も平成4~6年および平成8年から現在に至るまで、漁場環境保全のための環境指標および基準を策定するための調査を実施しており、これらの成果は平成11年(1999年)に施行された「持続的養殖生産確保法」で規定される漁場改善計画に活かされることになろう。
また、前述のように昭和54~56年に行った研究によって、モイストペレットは生餌ミンチに比べて汚染負荷を著しく軽減することが明らかにされ、多くの漁場でモイストペレットが使用されるようになった。最近ではさらに汚染負荷の少ないドライペレットへの移行が進み、漁場環境保全への意識は高まりつつある。
一方、漁場環境保全とは別の観点から、水質の良好な沖合での魚類養殖の可能性を検討するため、環境条件調査、実証試験などを昭和62年から平成5年にかけて実施したが、多大な施設経費やリスクの大きさから実用には至らなかった。
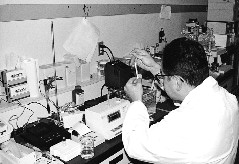
養殖魚の鮮度の測定
(2) 魚類種苗生産研究
三重県水産試験場における魚類の種苗生産は、昭和33年(1958年)伊勢湾分場において海産稚アユの種苗化に関する研究から始まった。その後、昭和38年(1963年)に、三重県立大学伊藤隆教授によって汽水他に生息するシオミズツボワムシがアユの仔魚飼育の好適餌料であることが明らかにされたのを受けて、同年に宮川のアユから採卵して種苗生産を行った。当時汽水を利用していた養鰻池で、餌料のワムシをネット採集してアユ仔魚に与え、全国で初めて人工孵化から稚魚までの飼育に成功し、1万尾の種苗を生産、養殖用種苗として配布した。
昭和40年(1965年)には米国ハンボルト大学のデビット教授がアユ養殖の研究視察に伊勢湾分場を訪れ、当時の担当技師が同教授の依頼を受け、指導のため渡米した。その後、昭和47年(1972年)からワムシの培養試験に取り組む等の技術開発に努めたが、研究は進展せず昭和50年(1975年)にアユ種苗生産試験は終了した。しかし、この時、餌として使用されたシオミズツボワムシは、現在でも数多くの海産魚類の初期餌料として使用されており、その餌料価値の発見は歴史的に高い評価を受けている。
一方、昭和35年(1960年)には、菰野町に湯の山養魚場が竣工し、ニジマスの種苗生産事業が始められた。外部から稚魚、親魚候補、親魚を購入するとともに発眼卵も購入し、初年度に稚魚47万尾を生産している。ニジマスは、外国から導入されたもので既に配合飼料もあり、当時最も進んだ種苗生産技術レベルにあった。湯の山養魚場では、ニジマスに加えてアマゴの種苗生産も行われ、見学者も多く訪れて県内各地区に種苗生産技術を伝えることに貢献した。湯の山養魚場は昭和42年(1967年)に内水面水産試験場(菰野町神森)に業務を移管したため、ニジマスの生産事業は昭和43年で終了した。
海産魚の種苗生産は、昭和42年(1966年)、瀬戸内海栽培漁業協会が前述した汽水性のワムシを餌料として、マダイの種苗生産に成功したのを契機に急速な進展を遂げることになる。尾鷲水産試験場では、昭和30年代からハマチ養殖に関する研究を盛んに行っていたことから、昭和45年(1970年)、魚類の種苗生産研究を開始すべく東京大学の指導の下に、初期餌料であるワムシ培養試験から着手し、ブリ種苗生産研究(水産庁指定調査研究)を開始した。また同年には、愛知県水産試験場尾張分場からクロダイの受精卵を入手して、体長2~3cmの稚魚約5千尾の生産に成功しており、これが三重県における海産魚類種苗生産の第1歩であった。ふ化仔魚の飼育は、パンライト水槽4個と屋外に7トンと、20トンのキャンバス水槽を設置して始められ、初期餌料には海産クロレラで培養したワムシとカキの受精卵が使用された。これらの研究と並行して、マグロ養殖技術開発企業化試験や中部電力三田火力発電所(温排水を利用した魚類飼育施設を持っていた)との共同研究としてブリの親魚養成試験も始めた。マグロ養殖技術開発企業化試験では巻き網で漁獲されたキハダマグロの人工採卵に初めて成功し、ふ化仔魚の飼育試験を実施している(近畿大学、水産庁遠洋水産研究所との共同研究)。一方、ブリの親魚養成試験は失敗し、健全卵を得ることができなかった。しかし、親魚養成研究としては、昭和48年(1973年)にマダイの早期採卵に成功したほか、クロダイ、イシダイ、ヒラメ、ノミノクチの自然採卵が可能となった。マハタは、この頃から既に新養殖魚種として注目されていたが、採卵はもちろん、成熟させることさえできなかった。
以上のように魚類種苗生産に関して一定の成果は得られたものの、これ以上研究を進展させるためには、研究施設の充実が必要であるとの判断から、昭和46年に魚類種苗生産施設整備計画が認められ施設設計の検討が始まった。その結果、良質の飼育水が重要であるとの観点から、建設地は尾鷲市元須賀利に決まったが、ここには陸路はなく通船に40分も要するという、陸の孤島といっても過言ではない場所で、電気がひかれたのは3年後の昭和51年のことであった。また、建設予算も十分ではなく、一部の施設は職員自らの手作りであった。元須賀利種苗生産施設での飼育研究は昭和48年(1973年)から始められた。昭和45年(1970年)から、元須賀利の研究施設が廃止(尾鷲水産試験場が尾鷲市古里に新設されたことによる)される昭和58年(1983年)までの13年間に、尾鷲水産試験場ではマダイとカサゴの種苗生産技術を確立し、海面生簀での2次飼育も含めて毎年2~8万尾の稚魚が安定して量産できるようになった。この他に、元須賀利の施設で種苗生産が試みられた魚種は、クロダイ、イシダイ、ヒラメ、イシガレイ、ムラソイ等があった(この間、研究担当者は研究外の苦労も数多く、例えば荒天時には施設まで通船が利用できないため、須賀利地区から徒歩で1時間、餌のワムシをリュックで背負って山越えの道を歩くといったことも再三ではなかった)。以上のような成果は、昭和50年頃から尾鷲水産試験場によって民間への指導が行われ、県内業者による種苗生産事業も行われるようになった。

カサゴのふ化直後の仔魚(約4mm)
以上のような種苗生産の技術開発は同時に餌料開発でもあり、シオミズツボワムシから始まった餌料は、クロレラによる培養からパン酵母、油脂酵母の導入によってワムシ培養の効率化と栄養の強化が図られ、さらにアルテミアの利用や配合飼料の改良が加わって一層発展した。また、親魚の成熟促進技術、病害対策技術など周辺技術の飛躍的な進歩もあった。現在の種苗生産技術は、この時期全国の水産試験場が競うようにして開発した技術が基礎となっており、日本の海産魚類の種苗生産研究は世界の最高水準にあると評価されている。
昭和59年(1984年)には、三重県水産技術センターが新設され、魚類の種苗量産技術の向上と親魚養成技術の確立を目的とした、新たな見地からの飼育研究が開始された。その結果、マダイ、ヒラメの産卵調整技術が確立され、早期及び抑制産卵が可能となった。その他、天然親魚から採卵したトラフグの種苗生産試験やバイオテクノロジー技術開発の一環としてヒラメの雌性発生に関する研究も行なわれた。ここで開発されたマダイ、ヒラメ、トラフグの生産技術は昭和63年(1988年)から稼働した三重県栽培漁業センターの魚類種苗生産事業に引き継がれた。この後、平成8年(1996年)には尾鷲市古江町に三重県尾鷲栽培漁業センターが新たに開所し、水産技術センター尾鷲分場が同センターと協力してこの最先端の施設を使用し、平成8~11年にカサゴの種苗量産研究を行い、10万尾以上の種苗の安定生産が可能となっている。このため、平成11年(1999年)には、栽培漁業センターの新しい生産メニューとしてカサゴも加えられることになっている。
現在水産技術センターでは、新魚種の養殖用種苗として、クエ、マハタの量産を目指して水産庁養殖研究所の協力を得ながら研究を行っており、平成10年には、クエ2万尾、11年にはクエ3万尾、マハタ1万尾を生産している。これらの技術もまた、平成14年(2002年)には栽培漁業センターに移転する予定である。
なお、カサゴや新魚種のクエ・マハタについての研究は、尾鷲栽培漁業センターの新施設が使用されており、これらの新たな成果は研究者サイドの努力の結果ではあるが、研究機器や施設の整備の重要性をも示唆しているといえる。