三重県水産研究に100年(創立百周年記念誌)
三重県水産試験場・水産技術センターにおける研究史のトピックス
1.イセエビに関する研究
日本における海産魚介類の種苗生産研究の歴史は、イセエビから始まったといっても過言ではない。既に明治32年(1899年)、ふ化飼育の試みが水産講習所(現東京水産大学)において実施されており、これが本研究の嚆矢となる。奇しくもこの年は、三重県水産試験場が設立された年でもある。本研究は、このように古くから開始されたわけであるが、ふ化幼生(フィロゾーマ)は比較的簡単に手に入れることが出来ても、成長させることが全くできなかった。これは、フィロゾーマの餌が何であるかが分からなかったことが最大の原因である。フィロゾーマは、親のイセエビと同様に、何度も脱皮しながら成長するわけであるが、この年代では、まず最初の脱皮をさせることが出来なかった。古い報告には最初の脱皮成功との報告例もあるが、現在の研究結果から見ると間違いであったと考えられる。
さて、名前からしてイセエビという程の本県の代表的水産物であるから、三重県もこのフィロゾーマの飼育研究に乗り出すこととなった。昭和7年(1932年)7月発行の三重県水産試験場時報(第27号)に「いせえびの人工孵化試験開始」との記載があり、それによると「三重県と言えば、大神宮鎮座の地として、又いせえびの産地として全国の児童にさえ知れ亘っているが、(中略) 予備的研究として昭和4年来着手している」とある。一方、三重県水産試験場事業報告には既に昭和5年度から「いせえび孵化飼育ニ関スル研究」が記載されている。したがって、実質的には昭和5年(1930年)が三重県での最初のスタートの年となる。以後、三重水産試験場事業報告によれば昭和7年まで研究が行われた。その方法は、基本的には海中に設置した小型生け賛網にフィロゾーマを収容し、電動式プロペラ等を用いて海水交流を図り、フィロゾーマが生育するかどうかをテストするという試みであったが、ほとんど成果が得られず研究は断念される。これが三重県におけるイセエビ種苗生産研究の最初の試みである。以後三重県では、イセエビについての研究は、小型エビの再放流による増殖試験や蓄養試験、また天然で採集される稚エビやガラスエビ(プエルルスと呼ばれる透明な稚エビ)を種苗とした養殖試験が研究の主体となる。 このような研究の方向転換はイセエビの主産県である、千葉県、静岡県、和歌山県、長崎県等においても基本的には同様であつた。 以上が三重県におけるフィロゾーマ飼育研究の第1期の経過である。
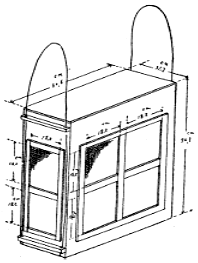
昭和5年に試作したイセエビ孵卵飼育槽
この後、戦争を挟んで20数年間イセエビの種苗生産研究は中断され、再び日本において研究が開始されるのは、昭和33年(1958年)野中・大島・平野(静岡県水産試験場、東京大学)によって、アルテミアというプランクトンのノウプリウス幼生がフィロゾーマの餌として利用できること、そして2回の脱皮を成功させたという歴史的な成果が発表されたためである(その後、ノウプリウス幼生を飼育して大きくしたアルテミアも餌として有効であることが分かった)。この成果を契機として、再びイセエビ種苗生産研究の火の手が全国的に広がることとなった。この、昭和30年代から40年代の半ばまで行われたのが第2期の研究ということになり、この年代は水産庁の指定調査研究という研究補助事業が、各県の研究を物心両面で支えた時代でもあった。県単独事業として研究を実施した県も多く、イセエビが漁獲される県でこの研究が行われなかった県はなかったといってよい。一方、大学でも、鹿児島大学において精力的な研究が行われ、三重県では、水産試験場はもちろん、鳥羽水族館なども研究に参加するというほど広範囲な機関で研究が実施された。この間、種々の面から飼育技術の改良に関する検討が行われたが、やはり主題は餌であった。餌の主体は前述したアルテミアであるが、単独投与では成長に限界があり、これに加えて多種多様な餌が、各機関で試験的に投与された。この間、三重県水産試験場(浜島)では昭和38年にメダカのふ化仔魚を与えることによって、当時としては画期的な成長結果を得、全国の注目を浴びた。第2期の研究では、フィロゾーマの飼育期間(約1年間)のうち、初期から中期についての問題はほぼ解決されたが、中期から後期にかけての問題は多く残された。ただし、神奈川県や静岡県では中期から後期にかけても多くの研究成果を得、特に神奈川県では、最終期のフィロゾーマまでの飼育に成功という画期的な成果を得た。三重県では記録上は、昭和37年から再開され、昭和44年までで打ち切られた(第2期の研究がここまでの成果を上げながら、何故終わってしまったのかは不思議な思いがするが、研究の困難さに多くの研究者が精根尽き果てたといったことではなかったかと当時の関係者の証言がある)。
第3期の研究は昭和55年7月、三重県浜島水産試験場において始まる。当時赴任した新場長の下に研究が再開されることとなる。因みにこの場長は昭和31年に、イセエビの交尾・産卵行動を日本で初めて記録・報告している。第2期までの研究をそれ以上に進展させるためには、主要な問題はやはり餌であった。この頃になると、マダイを主な対象として海産魚類の種苗生産技術が急速に進歩しつつあった。イセエビの餌として用いられたアルテミアは、魚類の種苗生産にも多用されたが、栄養的に問題があること、特に脂肪酸組成に偏りがあることが解明されつつあり、このアルテミアの栄養的な偏りをなくすための工夫が種々試みられていた。このような手法をフィロゾーマの飼育に応用し、改良していくとともに、さらに飼育環境の改善等の技術改良を進めた結果、フィロゾーマの成長が格段に促進されること、また生き残りが安定することが三重県浜島水産試験場によって初めて確認された。

小型ボウルを使った飼育実験(昭和60年ごろ)
この結果、後期フィロゾーマまでの飼育が容易となり、この様な方法で最終期まで飼育し、ガラスエビ(プエルルス)に変態させることが出来るのではないかという見通しもあったが、さらに種々の工夫を重ねても新たな研究の展開はなかった。この間、三重県浜島水産試験場(昭和59年から水産技術センター)以外には、この問題に取り組む研究機関はなかった。この第3期の研究が停滞しつつあった昭和62年に、最終的に成功の決め手となった新たな餌である、ムラサキイガイの生殖腺、主として卵巣の投与テストが開始される。そして、この新たな餌の開発によって昭和63年(1988年)5月12日、世界で初めてイセエビ幼生の完全飼育が達成されることになった。この間の飼育日数は307日、フィロゾーマの脱皮回数は28回であった。この変態したプエルルスは13日後、更に脱皮して稚エビとなった。この時成功した小型ガラスボウルを用いた飼育方法は、その後改良が加えられて標準的な飼育方法として確立され、実験規模の飼育では現在でもこの手法が用いられている。平成元年(1989年)になると、日本栽培漁業協会南伊豆事業場が新たにイセエビ種苗生産研究を開始し、現在では同事業場と連携を図りながら、種苗量産の技術開発を目指して今日も研究が継続されている。種苗量産のためには、ムラサキイガイ以外の安定的に入手可能な餌料の探索や人工飼料の開発、疾病対策、飼育技術の簡素化や飼育容器の大型化等まだまだ解決すべき課題は多く、千尾単位の量的生産技術の開発にはまだ多少の時間が必要な段階である。しかし、その基礎となる小規模の飼育実験では飼育技術はほとんど完成しており、最初の成功当時は、数千尾の初期フィロゾーマからやっと1尾の稚エビが生産されるというレベルから、現在では数尾の初期フィロゾーマから1尾の稚エビの生産が可能であるというような、著しい生残率の向上に成功している。
以上イセエビ幼生フィロゾーマの飼育研究に限定して、三重県を主体とした研究史を述べてきたが、水産技術センターではこの研究以外に、イセエビの資源管理手法の開発にも平成2年から精力的に取り組み、本県の主産地である志摩町和具のエビ刺し網を対象として研究を行ってきた。この研究では10万尾以上ものイセエビを測定し、その資料を整理解析するという多大な努力を行うとともに、新たな数値解析技術の開発をも行い、科学的な裏付けのある提言を行って、実際に現場でその成果が取り入れられつつあるあることを付記しておく。