2021(令和3)年度
『人権教育サポートガイドブック』活用のための講座 報告
2021年12月、『人権教育サポートガイドブック』活用のための講座を開催しました。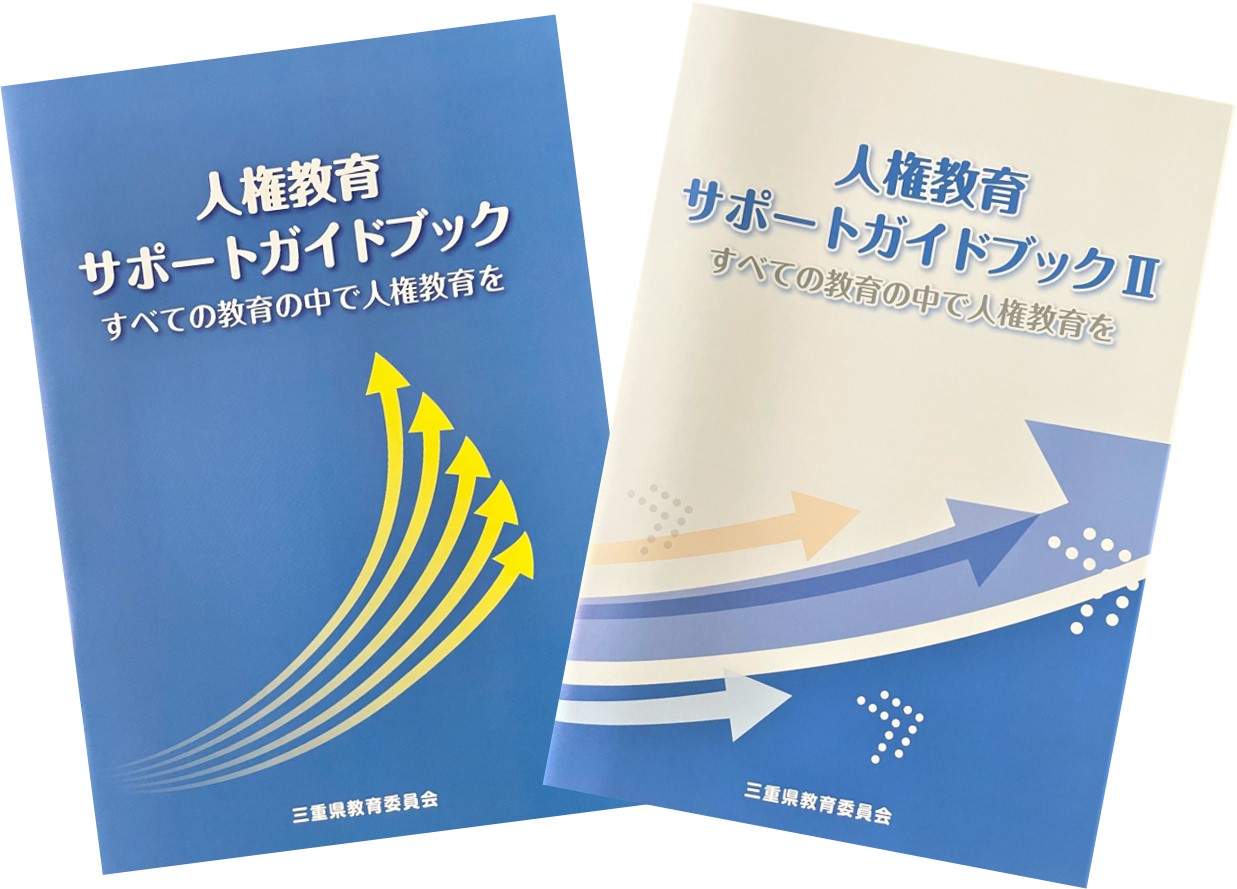
『人権教育サポートガイドブック』を活用した具体的な取組について、二人の教員から実践報告をしてもらいました。また、それをもとに、『人権教育サポートガイドブック』を活用した人権教育推進のための取組等について、参加者が交流しました。
この講座は、会場参加とオンライン参加のどちらも可能なハイブリッド形式にて研修を行いました。参加者のみなさんにご協力いただき、充実したグループワークを行うことができました。
以下、講座の概要を報告します。
12月24日(金)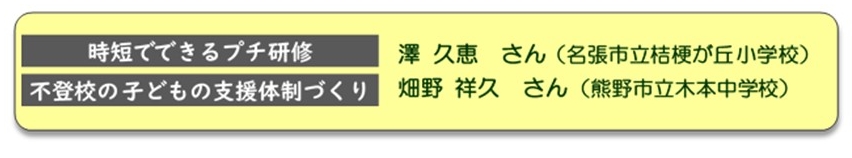
 澤さんからは、『人権教育サポートガイドブック』を活用した「プチ研修」の取組について報告がありました。桔梗が丘小学校では、校内研修とは別に、月2回程度自由参加で人権教育研修が行われています。わからないことを素直に「わからない」と言える等、人権教育についての共通理解や教職員の集団づくりの場になっている、とのことでした。
澤さんからは、『人権教育サポートガイドブック』を活用した「プチ研修」の取組について報告がありました。桔梗が丘小学校では、校内研修とは別に、月2回程度自由参加で人権教育研修が行われています。わからないことを素直に「わからない」と言える等、人権教育についての共通理解や教職員の集団づくりの場になっている、とのことでした。グループワークでは、澤さんが「プチ研修」で取り上げた内容から、被差別当事者が被っている不利益や生きづらさについて考えを出し合い、当事者の生きづらさに気づくことの大切さを確認するなど、「プチ研修」を実際に体験しました。
畑野さんからは、不登校の子どもの支援体制づくりのために『人権教育サポート
 ガイドブックⅡ』を活用した取組について報告がありました。教職員だけでなく関係機関とともに不登校の子どもについて共通理解をし、学校独自の「登校支援シート」をもとに子どもに応じた支援にあたることで、よりよい支援の方法を模索し多角的に対応できるようにしている等、いくつかの具体例について話がありました。『人権教育サポートガイドブックⅡ』の内容を提示することで教職員の共通理解が図りやすかったそうです。
ガイドブックⅡ』を活用した取組について報告がありました。教職員だけでなく関係機関とともに不登校の子どもについて共通理解をし、学校独自の「登校支援シート」をもとに子どもに応じた支援にあたることで、よりよい支援の方法を模索し多角的に対応できるようにしている等、いくつかの具体例について話がありました。『人権教育サポートガイドブックⅡ』の内容を提示することで教職員の共通理解が図りやすかったそうです。グループワークでは、これまでの経験等を出し合いながら、不登校の子どもの支援に大切なことは何か、について話し合いました。
【参加者アンケートより】
《時短でできるプチ研修》〇職員をつなげるという視点がよいと思いました。また、授業等、実践の交流もできるとよいですね。自校でも
OJTがありますが、参考にさせてもらいます。「あの人がいるから熱い」じゃなくて、組織として学習をして
いかなければならないですね。『人権教育サポートガイドブック』に載っていることを話のテーマにしなが
ら、みんなでざっくばらんに語り合う時間をつくってみたいと思いました。
〇自分も、初任のころから「人権教育ってどうすればいいのか」と考えてきたのを思い出しました。そして、そ
の度に先輩たちから「これはな…」と教えてもらったり、先輩どうしが話しているのをこっそりと聞いていた
りしたのを思い出しました。自分が気になったことを隠さずに聞けるというのは、教室でも同様に大切にすべ
きことだと思いました。子どもたちが安心して過ごせる教室にできるよう、これからも取り組んでいきたいで
す。
〇自身が経験も知識もない中で、経験のある先輩方に質問する機会があまりなく、「こんなこと聞いてもよいの
か?」などの葛藤が日々あります。澤さんの「プチ研修」は、若い先生だけでなくいろいろな先生方が自由に
参加できたり、話しやすいような約束事を決めたりしているのが、とても素晴らしいと思いました。
《不登校の子どもの支援体制づくり》
〇小学校は、どうしても担任だけでがんばってしまう傾向があると思います。でも、それでは子どものためにな
らないこともあると思います。「学校に来る」だけをゴールにするのでなく、「学校との関係を切らない」よ
うに、不登校児童の支援をしていこうと思います。まずは子どもの思い・保護者の思いを聞くことからです
ね!
〇関係機関や関わっていただいている先生方との「横の連携」の大切さは重々感じていますが、実際自分はでき
ているか、とふり返りました。今、自分のクラスには不登校等の状況になっている子どもたちがいて、日々
対応に頭を悩ませています。そんな中、やはり学年団などチームで対応することが不可欠と感じました。チー
ム力の向上を目指していきたいです。
〇学校に来ることだけをゴールにするのではなく、まず本人の気持ちを理解することや、本人と会えなくても保
護者とつながることを大事にしたいと、グループワークの中で感じました。また、子ども一人ひとりによって
対応の方法が異なると思うので、子どもそれぞれに対応の仕方を考え、いろんな先生に協力してもらいながら
すすめていきたいと思います。
《全体を通して》
〇『人権教育サポートガイドブック』は、事例だけでなく法律・条例なども紹介

されていて、若い先生が多い自校で人権について共有する際に活用していきた
いと思いました。事例を通して、人権についていろんなことを話し合いたいで
す。グループワークをする中で、いろいろな学校で取り組んでいること、困っ
ていることについて出し合い、自分にはない考えにも出会えて、とても勉強に
なりました。
〇『人権教育サポートガイドブック』を更に読みこんで、授業のあり方や考え方を他の先生に紹介できるように
なっていきたいし、多くの先生に知ってもらいたいと思った。学校独自で人権問題を考えていくのも大切だ
が、今回は同じ取組を行っている他校の先生方とも話すことができて、とても良い時間だった。
〇「どの学校に行っても、誰がやっても、という体制にしていきたい」という言葉が印象に残りました。一人ひ
とりが自分のこととして考えていく、そうなるには、まず自分が勉強していくということを大事にしたいと
思いました。
〇こうやって研修に来て討議をすることで、学べることがたくさんありました。「人権学習っておもしろい!」
ということに気づかせたいと、私自身も思うようになりました。教師が語ることが取組にもつながっていくと
思うので、学校に戻って返していきたいと思います。
〇オンラインでの参加でしたが、グループワークの際には少人数で話ができ、先生方の思いや取組を聞かせてい
ただけたことが、これからの自分のパワーになると感じました。また、澤先生がおっしゃったように、人権学
習は、どこの学校でも誰もが取り組めるものでありたいです。自分はまだまだ分からないことばかりですが、
学んでいきたいと思います。
〇人権教育担当をさせていただき、学習指導資料『みらいをひらく』や『人権教育サポートガイドブック』を参
考にさせていただく機会が増えました。改めて読んでみると、今まさに知りたかったことが載っていたり、ス
モールステップで考えられるようになっていたりして、本当にありがたいです。今後も活用していきたいと思
います。